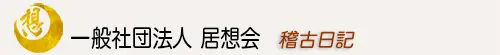アーカイブ
居想無外流居合道・剣術の稽古日記
令和七年の居合稽古日記
12月21日(日) 秋葉原・剣術:関戸光賀
 剣術の初心者稽古には、2名の方が参加されました。
剣術の初心者稽古には、2名の方が参加されました。
これをきっかけに、剣術の楽しさを理解していただければ嬉しいです。
難しいことは言いません。体をたくさん動かし、自然と体が技を覚えていくのが理想です。
また、1月4日の2回目は7名の参加予定です。刀だけでなく、木刀を振る仲間が増えていくのも楽しいことですね。
12月21日(日) 秋葉原・居合:中野瑞岳 指導補
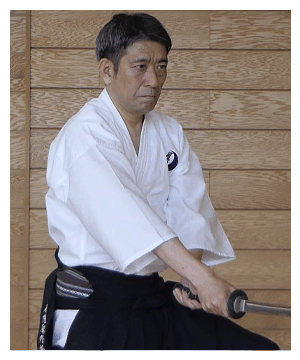 久しぶりの稽古の方もいらっしゃり始めた頃を思い出しました。
久しぶりの稽古の方もいらっしゃり始めた頃を思い出しました。
稽古を初めて間もない頃は、初めて見る動きだったり覚える事が沢山あって頭の中が一杯になってしまったのを覚えています。
軸を立てて、半身を切って、左手を使って等はどの様にしたら良いか最初はよく分からなかったと思います。
欲張っても一遍に身につけるのは無理ですので例えば最初は今日は刀を真っ直ぐ振る事と体が捻れない様に半身をしっかりきる事等と一つ二つに毎回目標を絞って行うと良いかもしれません。
繰り返していると、ある時気付いたら小さな積み重ねの結果多くの事が出来ていると分かったりします。また出来た事が連動していたりしますのでより一層向上したことが自分で感じる時がやって来ます。
今後もご一緒に稽古を続けて参りましょう。
まだ年内稽古はありますが、今日が私の担当では本年最後でした。無事に終わる事が出来たのは皆様の沢山のご協力を賜った結果と感謝申し上げます。
ありがとうございました。
12月21日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
 先週、平澤先生の五用、五応に続き、本日は五箇、走り懸りを行い計18形で年内の稽古の締めくくりといたしました。
先週、平澤先生の五用、五応に続き、本日は五箇、走り懸りを行い計18形で年内の稽古の締めくくりといたしました。
今回も鏡を利用して軸ブレ、刃筋等確認しながら稽古を進めました。
人により得意な形、不得意な形それぞれですが、稽古を重ねることによって正しい動きを習得していくよう心掛けたいものです。
今年も残すところあとわずか、会員の皆様には体調を崩すことなく新年を迎えてくださいますよう祈っております。
今年一年ありがとうございました。
来年4日から新たに稽古がスタートします。また稽古場でお会いいたしましょう。
12月21日(日) 品川・居合:大隅幸一 師範
 本日は基本稽古と形稽古の何れでも正しい基本の所作と動きが出来るよう心がけていただきました。
本日は基本稽古と形稽古の何れでも正しい基本の所作と動きが出来るよう心がけていただきました。
剣法と違い実際の相手が居ない居合稽古ですが相手が居ることを前提にしている基本や形の稽古でもあります。
更に精度を高めていくためにも仮想敵をも意識して動くことが出来るよう頑張ってもらいました。
残すところ十日で今年も終わろうとしています。
1年の稽古を振り返り各自それぞれの課題があると思いますが、来年も更に正確な所作・動作などを身に着けられるようお互い頑張りましょう。
今年1年ありがとうございました。
12月20日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
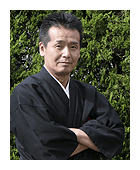 早いもので今年も残すところあと10日余りになりました。
早いもので今年も残すところあと10日余りになりました。
人数も適正で指導部員と手順の入っている会員さんの参加だった為、細かい部分について個別で見ていくようにしました。
下半身から上半身まで軸をしっかり立て、左右のブレがないように正中線を意識した身体捌きを心掛けて稽古を行いました。
本日で今年の稽古指導が終わりました。
稽古へ参加された会員の皆さんに怪我や事故もなく、無事に1年を終えることが出来たことは何よりの喜びです。
来年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。
12月14日、12月15日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 14日(日)基本の一、二の稽古を始めるに当たって宗家日記で解説されてました居合の動作にも通ずる「序破急」に関しての説明をさせてもらいました。
14日(日)基本の一、二の稽古を始めるに当たって宗家日記で解説されてました居合の動作にも通ずる「序破急」に関しての説明をさせてもらいました。
本日稽古のご夫妻が入会され丁度一年になります。
一年間の成果を確認する目的でお二人の「合わせ居合」を動画に撮り上達点と修正点をご自分達が認識し、これからの課題にされました。
15日(月)新人稽古先週に続き基本の一、二を通して抜刀、納刀の稽古と宗家日記で記されてました袈裟斬りに関して軸を崩さず両手を伸ばし、腰の左右の骨、上腕骨の左右4点の「面」を意識し袈裟の切り返しをする動作説明が端的で上手く伝えられたと思います。
有り難うございました。
12月14日(日) 池袋・剣術:関戸光賀
 腰に手を当てたときに指が触れる左右の骨の出っ張り2点と、同様に上腕骨の左右2点、計4点でできる「面」を意識します。
腰に手を当てたときに指が触れる左右の骨の出っ張り2点と、同様に上腕骨の左右2点、計4点でできる「面」を意識します。
袈裟の切り返しは、この面を板のように保ち、捻じらないように行ってみましょう。
刀は振るのではなく、切り返しの動きに合わせて、両手を前へ伸ばしていくようにします。
あとは軸を崩さないこと。
これだけで、袈裟の切り返しはOKです。
棒や薙刀など得物が変わっても、基本は同じです。
打太刀の注意点
形において打太刀は、仕太刀の良いところを引き出す役目を担う。
ただ斬られて終わるのではなく、斬られた後も相手を確かに見据え、残心を保ち、間を取るところまで決して気を抜いてはならない。
12月14日(日) 池袋・居合:和田冠玄 指導員
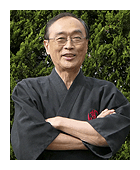 本日は池袋での担当稽古でしたが、ここを訪れたのはいつだったかと思うくらい久々の池袋した。いつもの城南・城西地区の稽古参加者とは少しだけ違った顔触れです。最近入会されたはじめましての方もいらっしゃいました。
本日は池袋での担当稽古でしたが、ここを訪れたのはいつだったかと思うくらい久々の池袋した。いつもの城南・城西地区の稽古参加者とは少しだけ違った顔触れです。最近入会されたはじめましての方もいらっしゃいました。
稽古では刀の取り方、刀の握り方、構え等々初歩的なところから体軸の維持や緩みから始まる動作の基本などにも注力頂き稽古してもらいましたが如何でしたか。
今後も池スポも含めて機会があればお伺いすることがあると思います。参加者皆さんと一緒に楽しみながら稽古できればと思います。
12月14日(日) 田町・居合:三浦無斎 師範代
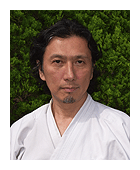 基本的なことの確認を中心に稽古いたしました。
基本的なことの確認を中心に稽古いたしました。
自分で話をしながら、あらためて「そうだったよな」と思うことがいくつかありました。
稽古回数が少ない方はもちろんのこと、慣れてらっしゃる方も
聞き飽きた基本に改めて意識を向けることで、違った気づきがあるのでは、と思ったりします。
私の担当は本日が年内最終でした。
上達への道は、地道に稽古を積み上げるのみだと思っていますので、来年も引き続き地道に共に精進して参りましょう。
12月14日(日) 市川・居合:平澤昂円 師範
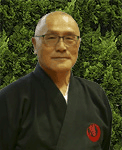 朝から寒い雨が降っていましたが稽古開始の12時には雨も上がりいつもの会員さんが参加されました。
朝から寒い雨が降っていましたが稽古開始の12時には雨も上がりいつもの会員さんが参加されました。
わたくしが担当させていただく稽古は今日が最後になります。
今年は体調が悪くまた骨折などをし本部また会員の方々にはご迷惑をおかけしました。自分の体の変化に正直に向き合うことの大切さを実感した一年でした。
稽古は五用、五応を来年につなげるように丁寧に抜いていただきました。来年も頑張りましょう。
12月11日(木) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
 通し稽古の際、途中で失敗した時に形を中断する、あるいは途中から始めることが何となく憚られます。多少間違えたからといって、形を中断させることはよろしくないと、私は教わってきました。通し稽古は形を最後まで通すのにもってこいです。ただ、形を一つ一つ微分して行う稽古も勿論大切ですので、偏ることなく稽古を重ねて行きたいものですね。
通し稽古の際、途中で失敗した時に形を中断する、あるいは途中から始めることが何となく憚られます。多少間違えたからといって、形を中断させることはよろしくないと、私は教わってきました。通し稽古は形を最後まで通すのにもってこいです。ただ、形を一つ一つ微分して行う稽古も勿論大切ですので、偏ることなく稽古を重ねて行きたいものですね。
というわけで、本年最後の西新宿稽古は五用の通しを行いました。
説明は部分的・限定的でした。個別に気になるところは教本で調べたり、指導部・師範に尋ねたりしてみてください。
立ちも一つだけ、胸尽くしを実施しました。こちらは形を微分しての稽古です。抜き、突き、構え、振りの各節目をしっかりと。習字で言うところの楷書でしょうか。特に不慣れなうちは節目を守ることを意識された方が良いかと思います。
本年、私が指導する稽古については本日が最終となります。今年から新たに開いた西新宿稽古場に来続けてくださる皆様には感謝を申し上げます。
来年も引き続き稽古を重ねまして、一緒に精進できれば幸いです。是非、よろしくお願い致します。
12月7日、12月8日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 7日(日)、当日はご夫妻のみの参加でしたので、基本及び五箇の稽古後、合わせ居合で、走り懸りの前腰、夢想返し、神妙剣を互いに向き合いながら何度も稽古しました。
7日(日)、当日はご夫妻のみの参加でしたので、基本及び五箇の稽古後、合わせ居合で、走り懸りの前腰、夢想返し、神妙剣を互いに向き合いながら何度も稽古しました。
さすがご夫妻、掛け声・動作・息もピッタリでした。
8日(月)前週に続き新人稽古のご夫妻、前回は日頃使い慣れない動作で筋肉痛もあった様でした。
帯の結び方、刀礼後は納刀、抜刀、基本の一、二を繰り返しましたが、稽古終了前には納刀も鞘を見ずに出来る様になり、これから一歩一歩前進されるお二人の姿が楽しみです。
アメリカは11月の最後の木曜日が感謝祭、翌日のブラックフライデーのセールが終わると一気にクリスマス商戦です。
クリスマス・ツリーのライトアップや飾り付けと寒くても暖かさを感じられる季節となりました。
12月6日(土) 秋葉原・居合:関戸光賀
 この日の稽古では、居合における「序破急」について学びましたので、この日記にて補足を兼ねて少し詳しく記しておきます。
この日の稽古では、居合における「序破急」について学びましたので、この日記にて補足を兼ねて少し詳しく記しておきます。
「序破急」は本来、能楽などの芸能において曲や舞の流れ・テンポの変化を示す概念ですが、居合においても重要な要素となります。
基本二の動きを例として、「序破急」を当てはめて考えてみます。
まず「序」は、柄に手をかけるまでの静の段階です。
殺気を抑え、呼吸を整えながら静かに右手を上げていく時間となります。
次に「破」。ここでは左半身を送り出し、相手との間合いを詰めてゆく段階です。
動きが生まれ、技が展開していきます。
そして最後が「急」。相手との間合いが一足一刀となった瞬間、右半身を大きく押し出し、逆袈裟に斬り上げます。
「急」の動きについては日頃から多くの注意点が語られていると思いますが、「序」や「破」は意識から抜け落ちやすい部分でもあります。
あらためて「序」「破」の意味や動きについて考察してみることは、居合の技についてより深い理解の向上につながることでしょう。
11月30日、12月1日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 11月30日、前週の形レビューとして18本通しをしましたが、特に稽古回数が少ない五箇と走り懸りの8本を中心に、どの形を通しても言える事が、右腕に力が入り真っ直ぐに振れてない点と鞘引きの甘さをポイントに又、神妙剣の左への転化の際の緩みと腹抜きも重点に稽古しました。
11月30日、前週の形レビューとして18本通しをしましたが、特に稽古回数が少ない五箇と走り懸りの8本を中心に、どの形を通しても言える事が、右腕に力が入り真っ直ぐに振れてない点と鞘引きの甘さをポイントに又、神妙剣の左への転化の際の緩みと腹抜きも重点に稽古しました。
12月1日、新たに入会されたご夫妻の新人稽古でした。
ご夫妻は前週見学後直ぐに居合道具一式をネットで注文されましたが、居合刀は注文後制作の為、日本からFedexで輸送されるものの五ヶ月を要する為、道着と帯、鞘付き木刀は私の物を貸与し配送される迄の対応となります。
普段使う事を意識しない股関節や膝の緩み、剣体一致で身体全体を使う動き、刀礼等の所作に興味を示されていました。
ご主人は東日本大震災時に米海軍士官として支援、救助で活躍された方です。
11月30日(日) 池袋・居合:宮澤和敬 師範代
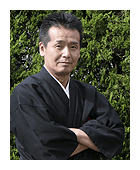 初冬らしい雲一つない青空が広がり、気温も少し高めで暖かい朝でした。
初冬らしい雲一つない青空が広がり、気温も少し高めで暖かい朝でした。
池袋で行った一般居合稽古の内容です。
無級の新人Mさんが演武会が終わった後も稽古へ参加されており、指導する側として喜ばしいことです。
2級の参加者が3名いたこともあり、足の入れ替え、真っ向と袈裟の素振り、抜刀稽古(横一文字、腹抜き、縦抜き)、基本の1と2を稽古した後の形稽古は1級の昇級審査形である「右」「胸尽し」「両車」を実施し、各自にポイントを伝えていきました。
演武会は終了しましたが、稽古へ参加する各自で次なる目標をしっかり掲げて、毎回の稽古をより充実したものとしてもらいたいと思います。
11月30日(日) 秋葉原・居合:関戸光賀
 今日は初傅位以上の方々の稽古ということで、皆さんすでに形の動きは頭に入っています。ですので、私は次の三つを心がけています。
今日は初傅位以上の方々の稽古ということで、皆さんすでに形の動きは頭に入っています。ですので、私は次の三つを心がけています。
まずは正しい動きへのアドバイスを三分の一。次に、その動きを徐々に修正し整えていくための三分の一。そして最後の三分の一は、頭の中を空にして、身体が自然に働くままに任せる時間です。
特にこの「最後の三分の一」はとても大切だと感じています。考えることをやめ、身体と心をひとつにして、ただ場に身を委ねてみる。そうすることで、普段は気づけない動きや感覚が立ち上がってきます。
今日の稽古が、それぞれの内側にある力を静かに引き出す時間となっていれば幸いです。
11月29日(土)品川・居合:髙橋武風 指導補
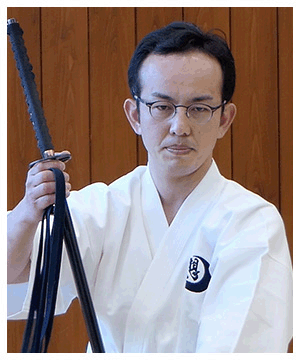 演武会から早くも1ヵ月ほど経ちました。
演武会から早くも1ヵ月ほど経ちました。
本日はゆっくりと動いて自分の身体の状態を確認しながら稽古しました。
ゆっくり動いてしっかり基本の動きを正確に覚えてましょう。
そうすれば早く動いた時にも正解に動ける事と思います。
また、ゆっくり動く事が目的とならない様に注意しましょう。
私自身も今一度基本に立ち戻り稽古して参りたいと思います。
11月29日(土)赤羽・居合:中野瑞岳 指導補
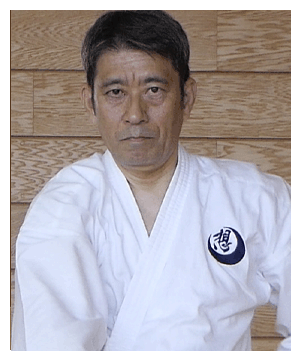 基本、形とも自身の体制や捌きは大事な事ですので注意しますが視点は己の方向になりがちになります。目の前に仮装敵と対峙している状況に立たされている情景を自身で想像する事も大切です。
基本、形とも自身の体制や捌きは大事な事ですので注意しますが視点は己の方向になりがちになります。目の前に仮装敵と対峙している状況に立たされている情景を自身で想像する事も大切です。
目先に迫ってくる敵に向けて適切な間合いをとり、刀の物打ちをしっかり相手の額や肩口、脇腹、水月などに打ち込む様に意識します。それだけでも自然と腕が伸び半身が切られた体全体を使った大きな動きのある刀捌きに繋がっていくのではと思います。
色々と意識する所が多いですが、其々のバランスが調和した時に美しい姿に仕上がっていくのでしょう。
またご一緒に稽古を重ねて参りましょう。
11月24日(月)田園調布・居合:山名宗孝 指導員
 田園調布稽古の2回目となりました。
田園調布稽古の2回目となりました。
手狭ながらも立地のせいか皆様にご参加頂けること、また稽古場所の予約にご協力頂けますこと、ありがたく思います。
稽古では刃筋を通すことについて少しお話ししました。抜刀の際に刀の取り方を都度お伝えしていますが、ご自身でも形稽古の中でも、時に確認して頂ければと思います。
11月24日(月)横浜中山・居合:和田冠玄 指導員
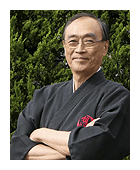 本日の稽古は演武会でのことを参加者夫々思い返して頂く機会になったかと思います。
本日の稽古は演武会でのことを参加者夫々思い返して頂く機会になったかと思います。
個別演武での緊張からくる違和感、合わせ居合のリーダーとしての出来栄え、審査を受けた方の新たな気付き等々。失敗とはいかないまでも、反省すべきことや良くできたと思えることなどいろいろな成果もあったのではと思います。新たな課題も見つかった方もいたことでしょう。
また次に向けて少しずつ精度を上げて行きたいものです。
11月23日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 私が日本に一時帰国をしていた為、皆さん3週間振りの稽古再開を楽しみにしておられ、形のレビューとして18本通し、その後各人が苦手の形を再度確認しながら稽古致しました。
私が日本に一時帰国をしていた為、皆さん3週間振りの稽古再開を楽しみにしておられ、形のレビューとして18本通し、その後各人が苦手の形を再度確認しながら稽古致しました。
見学者3名の内ご夫婦で来られた方2名は12月1日より初心者稽古をスタートされる事になりました。
今月8日の演武会では、熱のこもった皆様の演武をこの目で拝見し、宗家初め懐かしい方々ともご挨拶出来ました事、貴重な機会を頂き御礼申し上げます。
アメリカは今月27日が感謝祭(サンクスギビングデー)家族や友人達と集まり日々の恵みの感謝を捧げる祝日で、全米で過去最大の82百万人が大移動する予測もあり本日より各空港は大混雑です。
11月23日(日) 池袋・居合:浅野知義 指導補
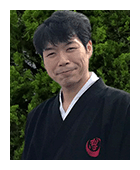 演武会が終わったタイミングでしたので、基本を確認しながら進めました。
演武会が終わったタイミングでしたので、基本を確認しながら進めました。
基本稽古よりも、なるべく多く形稽古したい。
と思う方もいると思いますが、土台となる基本はやはり大事です。
運足、半身の使い方、各素振り等々、形稽古にも必ず活きてきます。
舞台などで緊張したときに出てくるのが、普段稽古している動きです。
いざという時に焦らないよう、普段からしっかり確認していきましょう。
11月23日(日) 池袋・居合:中野瑞岳 指導補
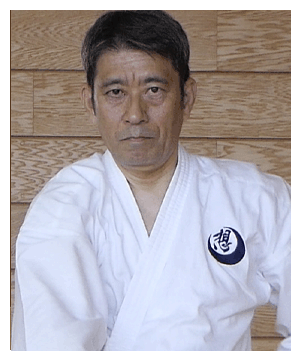 演武会が終わり写真や動画がホームページに記載されています。
演武会が終わり写真や動画がホームページに記載されています。
自らの姿を振り返り、舞台で演武したときの状況を思い起こされたのではないでしょうか。
上手く出来きて嬉しかったり、出来なくて観るのも気恥ずかしくなってしまったりなどさまざまな思いが込み上げて来た事と思います。
私はいつも良いところよりも見る度にこうすれば良かったなどと反省点がたくさん出て来ます。
反省点など演武会で感じた事は強く印象に残って行きますので日頃の稽古でも時々、思い起こしてみると自身の技量向上のヒントとして活かせると思います。
通常稽古が始まっています、良い事は励みに、反省点は糧として新たな気持ちで日々の鍛練に励んで参りましょう。
11月23日(日) 田町・剣術:関戸光賀
 通常の剣術稽古に加え、当面は週末に薙刀と棒、平日は小太刀の稽古を行うつもりです。
通常の剣術稽古に加え、当面は週末に薙刀と棒、平日は小太刀の稽古を行うつもりです。
長い武器と短い武器、重いものと軽いもの、その扱いの基本は共通しています。
道具の違いは、互いに不足している点を教えてくれるということにあります。
11月16日(日) 市川・居合:平澤昂円 師範
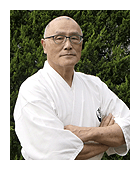 演武会が終わって初めての市川稽古です。演武会に参加された会員さんから、舞台に上がったら頭が真っ白になってしまい会員ページの動画を見て反省しきりだそうです。
演武会が終わって初めての市川稽古です。演武会に参加された会員さんから、舞台に上がったら頭が真っ白になってしまい会員ページの動画を見て反省しきりだそうです。
参加したからこそ客観的に自分の居合がみられ今後の稽古の方向性が明確になりいい経験になったと思います。
私も十数回参加させていただいておりますがいつも恥ずかしい思いをしています、居合は難しいけど自分を見つめるいい機会です。また一歩ずつ歩んで行きましょう。
11月15日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
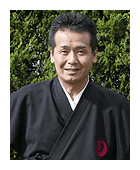 ちょうど一週間前に演武会が無事に終わって一息つく間もなく、指導部の面々や稽古熱心な会員さんが本日も滝野川武道場へ集まりました。
ちょうど一週間前に演武会が無事に終わって一息つく間もなく、指導部の面々や稽古熱心な会員さんが本日も滝野川武道場へ集まりました。
演武会では指定型や各自が選んだ形を集中的に稽古されていたと思うので、本日は改めて全ての形を稽古することにしました。
基礎稽古は足の入れ替え、真っ向素振り、抜刀稽古(横一文字、逆袈裟、腹抜き、縦抜き)を行い、いつもより早めに切り上げて、形を各4本行う18本通し稽古を行いました。
最後の18本目となる「右の敵」まで、皆さんの集中力が途切れることなく稽古を終えることができました。
11月3日(月) 秋葉原・居合:大隅幸一 師範
 いよいよ今週の土曜日に演武会となりました。
いよいよ今週の土曜日に演武会となりました。
本日は自主稽古前に、私と1級の方2名の3名で入場・独演形を含む方演武・退場までの一連の動きを行い皆さんで確認してもらいました。
その後は1部と2部の自主稽古を行っていただき、皆さん真剣に頑張っておりました。
演武会に向けて稽古してきましたので、その成果を出せるように頑張りましょう。
11月3日(月) 秋葉原・古武道:関戸光賀
 演武会に向けた剣術のシミュレーションを行いました。
演武会に向けた剣術のシミュレーションを行いました。
これまで、自分の担当する形について一生懸命稽古を重ねてきましたが、今日は出入りに伴う礼などの所作も含め、さらにギャラリーのいる中での演武稽古となりました。
このような稽古を一度経験しておくことで、舞台度胸がつき、本番でもこれまでの成果を十分に発揮できると思います。
皆さん、自信をもって臨んでください。
11月2日(日) 滝野川・居合:浅野知義 指導補
 本日も演武会に向けた稽古でした。
本日も演武会に向けた稽古でした。
演武会直前です。
万全の状態で演武出来る様、体調もしっかり整えていきましょう。
11月2日(日) 横浜中山・居合:和田冠玄 指導員
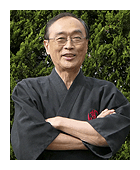 本日は演武会を来週に控えての稽古日でしたが、他の複数の稽古場の稽古開催がありましたので横浜は少人数での稽古でした。演武会参加の傳位の方にはご自身の演武形を、新人の方には基本の一、基本の二を稽古それぞれ稽古してもらっています。
本日は演武会を来週に控えての稽古日でしたが、他の複数の稽古場の稽古開催がありましたので横浜は少人数での稽古でした。演武会参加の傳位の方にはご自身の演武形を、新人の方には基本の一、基本の二を稽古それぞれ稽古してもらっています。
傳位の方は演武会に向けて細かいことを確認しながらの稽古。しっかり準備できたことと思います。
新人のSさんは数日前に入会したばかり。今回の演武会には参加できませんが来年の演武会ではステージ上で演武している姿を見たいですね。
11月2日(日) 市川・居合:平澤昂円 師範
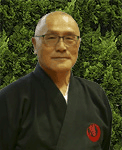 演武会まで残すところあと二回の稽古になります。
演武会まで残すところあと二回の稽古になります。
参加者の多くは前日の演武会全体稽古に出られていますので
鏡を見ながら目線、歩行、礼の姿勢を再確認です。
一部、二部とも入退場。立ち位置。形の動きを数回稽古をしました。どんどん上手くなります。稽古は嘘をつきません。
体調に気を付け自信をもって演武会の舞台に立ちましょう。
11月2日(日) 秋葉原・居合:三浦無斎師範代
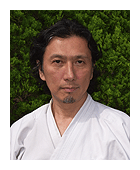 演武会目前です。
演武会目前です。
これまでしっかり稽古してきたので、あとは気持ちです。
目線を上げて堂々とやってやりましょう。
11月1日(土) 田町・古武道:関戸光賀
 演武会まで、いよいよあと1週間となりました。
演武会まで、いよいよあと1週間となりました。
お休みの日にもかかわらず、多くの方が参加してくださり、充実した稽古となりました。
指導部の皆さんも、手順がしっかりと頭に刻まれており、スムーズな進行ができたと思います。
これから直すべき点、伸ばすべき点を明確にして、残りの日々を大切に過ごしていきましょう。
10月30日(木) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
 何もしないことの難しさを感じております。
何もしないことの難しさを感じております。
抜刀時に右腕をほとんど動かさないことは、特に宗家稽古に出ている方々は頻繁に耳にするところかと思います。なお、縦抜においては不慣れなうちは刃が眼前を掠めかねませんので、くれぐれもゆっくり動くようにお願いしております。
形としては左月、陽中陰などがわかりやすいでしょうか。いずれも座り技で動作がしにくいですが、良い稽古となります。本日はこれらを実施致しました。
陽中陰の構え直しから立ち上がり、斬りの動作は教本を参照されるのが良いと思います。稽古の内容にも依りますが、あまり腰が低すぎたり前傾しすぎると体を痛めます。過ぎたるは及ばざるが如しということで。
演武会が近いです。演武や、あるいは出稽古などで環境が違う場所での動作は何かと動きにくく感じるものかと思います。環境を変えることはできませんが、自身を変えることで対応を試みて下さい。一例として、私は呼吸を意識しております。
それよりも何よりも、楽しむことが第一です。是非とも、楽しみながら日頃の稽古の成果を披露できると良いですね。成功をお祈りしております。
10月12日、16日、23日、26日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 日本での演武会が近づいて、その熱気はセドナまで伝わってきます。
日本での演武会が近づいて、その熱気はセドナまで伝わってきます。
そこで上記日程で日本の演武会と同様に指定形と合わせ居合、独演形、入退場、演武位置等シュミレーションの稽古を致しました。
26日はアメリカ在住30年以上の日本人ご夫妻が定年退職後、最近セドナに最近引っ越しされ、見学に来られましたので人前で演武の流れを披露出来たのも非常に良い経験でありました。
10月26日(日) 市川・居合:平澤昂円 師範
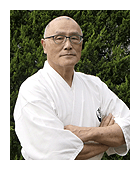 お岩神社の奉納演武が無事終了したと思ったらもう演武会が迫ってきました。
お岩神社の奉納演武が無事終了したと思ったらもう演武会が迫ってきました。
一部。二部の稽古を反復し体に覚えこませること、その上で
稽古場では丁寧にすること本番ではどうしても早く振るきらいがあります。自分をコントロールするのは大切と思います。
後2週間悔いないように稽古をしあとは演武会を楽しみましょう。
10月25日(土) 田町・居合:和田冠玄 指導員
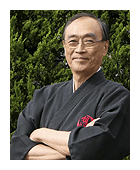 本日は演武会に向けての稽古、初めに刀の取り方、納刀他の所作、目線など基本的なところを確認してもらい稽古しています。
本日は演武会に向けての稽古、初めに刀の取り方、納刀他の所作、目線など基本的なところを確認してもらい稽古しています。
一部の入退場の稽古では1回目を終えたところで注意点等を指導確認してもらいましたが、2回目のシムレーションでは上手く修正出来ましたか。
2週後は演武会本番です。曖昧なところを確認して正しい動作を意識して、不安無しで本番に臨めるように稽古出来ると良いですね。
10月19日(日) 秋葉原・居合:大隅幸一 師範
 天候はよくありませんでしたが金木犀の香りがあちこちでしておりました。
天候はよくありませんでしたが金木犀の香りがあちこちでしておりました。
剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
演武会まで20日となりました。
本日の参加者は全員が演武会は初めての参加でしたので、最初に演武会1部演武形を稽古しました。
その後に演武会シミュレーションとして入場・演武・退場の一連を通して演武開始位置などを確認しながら行ってもらいました。
全体を通しては初めてで戸惑いながらも頑張っておりました。
本番ではさらに緊張しますが頑張ってまいりましょう。
10月18日(土) 滝野川・居合:浅野知義 指導補
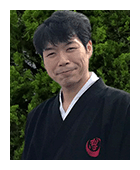 演武会が近いので基本稽古は早めに終わらせて、後半は自主稽古としました。
演武会が近いので基本稽古は早めに終わらせて、後半は自主稽古としました。
まだ演武会まで時間はありますので、本番でいい演武ができるよう、しっかり稽古していきましょう。
10月13日(月) 横浜中山・居合:和田冠玄 指導員
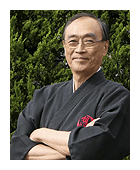 本日の稽古では基本を大切に出来るだけ丁寧に正しい動きが出来るように稽古しています。
本日の稽古では基本を大切に出来るだけ丁寧に正しい動きが出来るように稽古しています。
演武会に参加される方は御自身の技量を上げるように目標をもって、その課題を意識して稽古していると思いますが、演武会のように「観てもらう演武」では所作や形から次の形に移る際の動作も大きなポイントになります。
普段の稽古で曖昧にしたままで見過ごしていることや、何となく疑問に思いながらもやり過ごしているようなことに注意を向けてみることも大事です。そして演武会前の稽古では普段の稽古と違って個別の稽古時間がありますので普段「?」と思っていることを確認するいい機会かとも思います。
演武会まであと一か月を切りました。本番では思いっきり演舞できるように頑張って稽古していきましょう。
10月13日(月) 秋葉原・居合:岩田和己 指導員
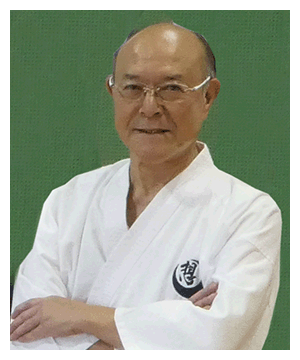 演武会まで一か月を切りました。
演武会まで一か月を切りました。
本日は基本稽古も含め演武会を念頭に置いて稽古を進めました。
今回初めて参加されるかた、また何度も参加されているかたも演武会が近づいてくると緊張感が高まってくるのは私だけではないと思います。
当日まで、稽古ができるのはあと数回です。基本稽古にしても形稽古にしても正しい所作を確認しながらゆっくり動いてみてください。
演武会であれ、普段の稽古であれ速い動きを求められるものではありません。
まして、演武会となると極度の緊張から本来の形を間違って演武することもあります。
ですから、稽古に参加されるときは、気負わず、正しい動きを七分の力で演武してみてください。
そして、演武会を終えた後には、きっと今までとは違った充実感を得られることでしょう。
演武会まであとわずか、ともに精進していきましょう。
10月2日、3日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 両日共、前回撮った動画で各自の癖・修正点が解りましたので今回の稽古ではそれぞれの課題を克服すべき、立った時の姿勢、斬り終りの姿勢、目線、基本の一、二の抜刀から振りかぶりを何度も繰り返し、形は真、夢想返し、胸尽くしを稽古しました。
両日共、前回撮った動画で各自の癖・修正点が解りましたので今回の稽古ではそれぞれの課題を克服すべき、立った時の姿勢、斬り終りの姿勢、目線、基本の一、二の抜刀から振りかぶりを何度も繰り返し、形は真、夢想返し、胸尽くしを稽古しました。
5日の稽古後は夜空を明るく照らす中秋の名月、アメリカではハーベスト・ムーン(収穫月)と呼ばれる満月を楽しみました。
10月5日(日) 池袋・剣法:関戸光賀
 演武会に向けた稽古にも、いよいよ熱が入ってきました。
演武会に向けた稽古にも、いよいよ熱が入ってきました。
自分の行う居合や剣法の形が定まり、それに集中して稽古を重ねることで、体が自然と練れてきます。
終わってみれば、他の形の練度も上がっていることに気づくことでしょう。
また、歩き方や立ち座りの所作、立ち姿などにも意識を向けて稽古していることと思います。
そうした心がけは、きっと良い結果をもたらします。
どうか、今この一瞬を大切に、稽古に励んでください。
10月5日(日) 池袋・居合:中野瑞岳 指導補
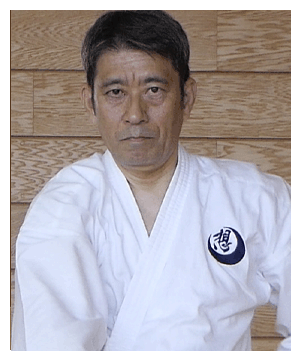 演武会に向けて稽古が始まり少しずつ気持ちも高まって参りました。
演武会に向けて稽古が始まり少しずつ気持ちも高まって参りました。
初めての方はどんな感じなのか不安な気持ちが芽生えたりしていないでしょうか。
私は還暦過ぎですが今回2部はシニア剣法で初演武です。慣れない場所で上手く間合いが取れるかなど心配の方が大きいですが良く出来た姿をイメージする様にしています。
シニア層も新しい事にチャレンジしています、皆さんが今の力を演武会で十分に発揮される様に微力ながら応援しております。
巡り合った大切な機会で舞台に立つ事はとても良い経験になり記憶の1ページとして残って行くでしょう。終わった後に良かった楽しかったと思える様にご一緒に頑張りましょう。
10月5日(日) 秋葉原・居合:大隅幸一 師範
 演武会まで1か月余りとなりましたので、本日は演武会を意識しての稽古としました。
演武会まで1か月余りとなりましたので、本日は演武会を意識しての稽古としました。
基本稽古でも形稽古でも同様に動きと所作いずれも疎かにならないように意識を持つことが大事です。
慣れてくると雑になる動きなどが出てきやすいです。
初心を忘れるべからずと言うように常に基本を意識しましょう。
演武会という目標に向け自己レベルを高める良い機会ですので共に頑張りましょう。
10月4日(土) 赤羽・居合:宮澤和敬 師範代
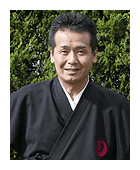 寒暖差が激しくなってきたので体調管理にご留意下さい。
寒暖差が激しくなってきたので体調管理にご留意下さい。
今回も手順が入っている会員さんの参加だった為、説明は少なくポイントだけをお伝えし、刀を多く振っていただきました。
演武会で同じ組になるメンバーはいなかった為、通常の流れで居合稽古を行いました。
演武会の広い舞台では軸の横ブレが目立つ為、仮想敵の方向にしっかり身体を向けて正中線を常に意識した動作を心掛けていただきました。
また、目線が下がると首から頭頂部の軸が前にズレてしまうので、目線をしっかり上げることも注意していただきました。
演武会に向けて、細かい所作の部分も大切にしていきましょう。
10月2日(火) 西新宿・居合:小井 健熙 指導員
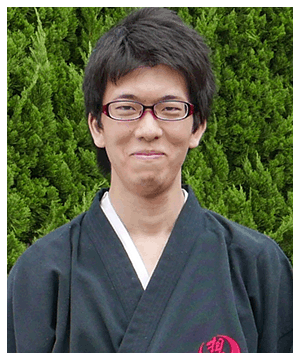 本日は級の方のみの参加でした。とは言ってもやることは変わりません。
本日は級の方のみの参加でした。とは言ってもやることは変わりません。
立ち姿勢の確認から始めた稽古ですが、思えば最初にお伝えしたことが全てでしたね。初動でも斬り終わりでも姿勢を崩さぬように、ということでした。鏡がありましたので視認しやすかったと思います。そのうち、足元の感覚などでも察せられると良いです。私も修行中です。
特に斬り終わりの姿勢は指摘させて頂きました。斬り終わりで咄嗟に動けるような、と説明を致しましたが、演武会向けには見目のことを話すべきでしたね。いずれにせよ中庸な姿勢を保つことは重要です。残心を忘れないようにしましょう。
参加者の演武形に沿いまして真・左月を実施しました。左月は顕著ですが、左と体捌きを上手く活用しないと抜刀が叶いません。逆に、右手は真ん中で刀を取った位置で完全固定をしても抜刀できます。右利きの方が多いと思います。左の運用を強く意識しましょう。
9月25日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 11月の演武会に向け日本の皆様が一層稽古に励んでおられる雰囲気が伝わってまいります。
11月の演武会に向け日本の皆様が一層稽古に励んでおられる雰囲気が伝わってまいります。
少しでもその雰囲気を感じようと、日曜日参加のご夫妻も加わり稽古時の動画を初めて撮り自分達の動きを見てもらう事にしました。
自分は出来ていると思っている動きや所作も動画で見ると一目瞭然で色々と修正点、改善点が見つかり、又動画で撮られる緊張感も感じてもらいながら狭い
道場で前後左右気を付け何時もとは違った稽古となりました。
9月23日(火) 横浜・居合:和田冠玄 指導員
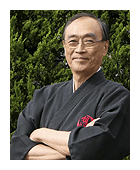 本日の稽古で演武会意識して出来るだけ正しい動作で丁寧に稽古すること、また抜刀前、納刀以降の所作にも注意を向けて稽古して貰いました。
本日の稽古で演武会意識して出来るだけ正しい動作で丁寧に稽古すること、また抜刀前、納刀以降の所作にも注意を向けて稽古して貰いました。
来週から本格的に演武会に向けての稽古が始まります。演武会までは一月以上は有りますが稽古回数を数えると思うほど多くはありません。それぞれ課題をもってしっかり稽古していきましょう。
9月21日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
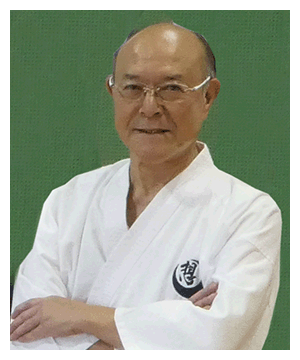 本日はいろいろな場所で稽古が行われ、市川では普段より少なめの参加人数となりました。
本日はいろいろな場所で稽古が行われ、市川では普段より少なめの参加人数となりました。
11月の演武会における昇傳、初級審査に向け補習を要請される方々がありました。
演武会まであと一か月半ほどです。今日の補修は平澤先生に見ていただきました。
今日の形稽古も受審者の指定形を中心に稽古いたしました。
各稽古形のポイントとなる箇所をお伝えし、それをもとに稽古を重ねていただきました。
やはり審査に臨む方々は、目つき、動きにもなんとなく気負いが感じられます。
稽古の段階では、もっとリラックスして、正しい所作で動けるようゆっくり確認しながら稽古して行きましょう。
諸事情により演武会に参加されない会員さんも、次回は参加するという意識をもって稽古に励んでいただきたいと思います。
9月21日(日) 池袋・剣法:五島博 師範
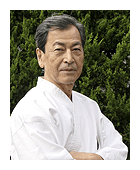 何時ものとうり基本稽古で身体をほぐした後、きたる演武会を考慮し形稽古は刃引きの形五本の稽古を実施しました。
何時ものとうり基本稽古で身体をほぐした後、きたる演武会を考慮し形稽古は刃引きの形五本の稽古を実施しました。
居合と異なり剣法は向かい合う相手がいる立ち合いとなりますので敵との間合をつかみ正中線をあわせ中心線をずらさず敵に向かい進むことそして打太刀に対し正し位置に剣を打ち降ろす事、特に初太刀の打太刀との間合(距離)を正しく保って打ち込む事で二刀目以降の打ち込みを正しい位置に送ることが可能になります、言い換えれば初太刀の位置が正確でなければ二刀目以降の打ち込み位置がズレてしまう事になると認識しましょう。
9月21日(日) 秋葉原・居合:小井健熙 指導員
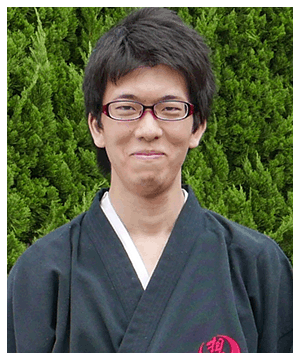 正中線とは何ですか?
正中線とは何ですか?
と、問われることがあります。私自身上手く説明できないので、他の指導担当や先生方の説明を聞いて腑に落ちたものを解とすれば良いと思います。ともあれ、今日はそんな正中線を意識しての稽古でした。
形は向抜、両車、響返しを実施してます。刀を正中線から外さず、ということをいずれも口喧しく話しました。何故外してはいけないか。様々に理由はありますが、今日の稽古では刀を扱いやすくするため、と説明しております。特に両の手で刀を持っている際、その両手が正中線から大きく外れていると身体が操作しにくいかと思います。ピンとこない方は今まさにやってみるとよろしいかと。刀を持たず徒手でも感じられることと存じます。
刀を扱いやすい、すなわち長く稽古していても疲れにくく、身体を壊しにくいことに繋がります。少々概念的な言葉ですが、自分のものにできるようにお互い稽古に励みましょう。
9月21日(日) 池袋・居合:関戸光賀
 皆さんの居合を拝見して心に残ったこと。
皆さんの居合を拝見して心に残ったこと。
動の躍動感、静の佇まい、そして形を繋ぐ所作の品格。
これこそが、居合の美であると感じました。
9月20日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
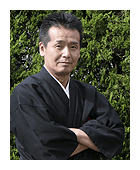 先週までの猛暑が落ち着き、朝晩はだいぶ過ごしやすい気候になりました。
先週までの猛暑が落ち着き、朝晩はだいぶ過ごしやすい気候になりました。
手順の入っている会員さんの参加だった為、説明は少なくポイントだけにして、刀を多く振りながら、各自の課題を修正していただきました。
演武会で昇級昇傅位審査を受けるМさんとKさんから補習の希望があったので、中野指導補に対応していただき、第1回補習を行いました。
補習と自主稽古時間が終わった後に2人が全体稽古へ戻ってきたので、審査形の「右」「胸尽し」「野送り」「響返し」「無想返し」を形稽古に組み入れてポイントをお伝えしました。
演武会までの稽古回数は限られています。
それぞれの課題と向き合い、意識を集中しながら稽古していきたいと思います。
9月20日(土) 田町・居合:大隅幸一 師範
 秋彼岸の入りの今日は以前の猛暑より気温が下がりましたが湿度が高く爽やかとまではなりませんでした
秋彼岸の入りの今日は以前の猛暑より気温が下がりましたが湿度が高く爽やかとまではなりませんでした
本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
基本稽古と形稽古のいずれでも丁寧に動くようにしていただきました。
動きに加え所作も基本を大事に丁寧に行うように伝え稽古していただきました。
本日は真・胸尽し・水月・前腰の型の稽古を行いましたが、特に注意していただいたことの一例は、腹抜きで切っ先が鯉口に収まっていること、突きは正確な位置に突くことなどでした。
速くてもゆっくりでも正確に行えるように稽古しましょう。
基本でも形でも基本的なことを正しく行えるようにするのが稽古です。
いくら指導で伝えても自分が意識しなければできませんので頑張りましょう。
9月15日(月) 田園調布・居合:山名宗孝 指導員
 新しく田園調布稽古場所を開くことができ、初回の稽古となりました。
新しく田園調布稽古場所を開くことができ、初回の稽古となりました。
施設予約において、ご協力を頂き施設利用に至りましたこと、この場を借りて改めて御礼致します。今後とも宜しくお願い致します。
稽古場所はアクセスが良く、新しい場所ということもあり、多くの方に参加頂きました。その為少々手狭となり、稽古では形を選ぶ必要がありましたが、皆さま縮こまった切にならず、周りとの位置取りを意識し、刀を振っておられました。
手狭ならばそれに対応し、形を限定せず、工夫を凝らして稽古を考えたいと思いました。
新たな稽古場所、快活な稽古ができるよう取り組みたいと思います。
9月14日(日) 品川・居合:大隅幸一 師範
 毎日蒸し暑い日が続いておりますが、稽古場は空調で調節しながらの稽古となりました。
毎日蒸し暑い日が続いておりますが、稽古場は空調で調節しながらの稽古となりました。
本日も基本と形でそれぞれ注意していただくポイントを絞って稽古していただきました。
稽古した形で、特に陽中陰の抜刀での左半身の捌きかたに注意していただきました。
左半身を縦の捌きで左足を右足の後方に下げて抜刀し敵のひざ下を斬りつける動きをしますが、左足が内側に回り込んで抜刀している場合があります。
右手で抜刀するのではなく、鯉口から切っ先が抜けるまで左半身と鞘引きの捌きで抜きつけていくようにします。
難しい捌きですが稽古を積み重ねて習得していきましょう。
9月13日(土) 秋葉原・居合:三浦無斎 師範代
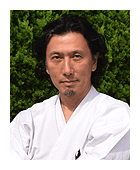 演武会が近づいて参りました。
演武会が近づいて参りました。
これを目標に精度を上げるよう稽古に向き合っていきましょう。
まだ時間がありますから、”自分流”になってないか、もう一度丁寧に見直してみましょう。体捌きは大きすぎないか、小さすぎないか、敵を正確に捉えているか、刀の軌道は基本通りか・・
”できた”と思った時ほど”見直す”時かもしれません。
謙虚に地道に続けて参りましょう。
9月7日(日) 池袋・剣術:関戸光賀
 演武会に向けて、剣法の稽古を始めました。
演武会に向けて、剣法の稽古を始めました。
今日は初日。何をすべきかを明確にする大切な一日です。
演武会までにはまだ時間があります。基本に立ち返り、曖昧になっていた部分を一つひとつ修正していきましょう。
こうした積み重ねの日々こそが、すべての動きのパフォーマンス向上につながります。
9月7日(日) 池袋・居合:和田冠玄 指導員
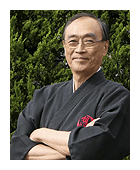 本日の稽古では基本動作を確認してもらい夫々の良くない癖を修正することを意識して頂いてます。
本日の稽古では基本動作を確認してもらい夫々の良くない癖を修正することを意識して頂いてます。
刀の取り方から抜刀への動作、足の運び、体の裁き、切り終わりの態勢等等、それぞれ癖になっていて気付かないでやり過ごしていることに気付かれたことが有ったかと思います。
もしかしたら間違った動作を正しいと動きと思い込んでそのままにしていることもあるかもしれません。
先ずは正しい動作を確認して修正すべきところは意識して稽古することが大切です。正しい動作を丁寧に繰り返して稽古することで少しずつ技量の精度を上げていければと思います。
9月6日(土) 田町・居合:髙橋武風 指導補
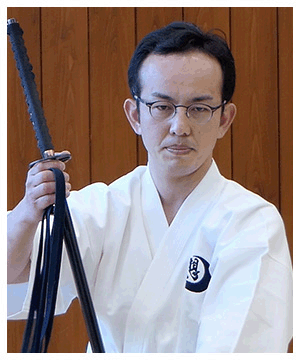 何事も正しい姿勢って大事ですよね。居合でも同じ事が言えるかと思います。
何事も正しい姿勢って大事ですよね。居合でも同じ事が言えるかと思います。
特に基本の平正眼の構えが非常に重要だと思っています。
土台となる構えですので、そこがずれてしまうと正しい技となら無くなってしまいます。
土台が歪んでいると高い建物が建てられないのと似ていますね。
今一度鏡の前で姿勢の確認をして頂ければと思います。
暑い日が続いていますので体調には気をつけて稽古を続けて参りましょう。
9月6日(土) 品川・居合:五島博 師範
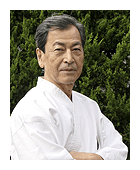 台風一過の晴天の朝、稽古場に着く頃は何時もの猛暑が始まっていました、体調に注意し給水を小まめに稽古を進めました。
台風一過の晴天の朝、稽古場に着く頃は何時もの猛暑が始まっていました、体調に注意し給水を小まめに稽古を進めました。
今日の参加者は稽古回数の多い方々だったので居合の動きの原則となる最速最短を目指すためにどう動くかを考えて稽古が出来るように伝えて稽古を実施しました。最速最短を得るために無駄な動きを排除し刀を軽く扱う為に刀の重心を体軸近くで扱うなど体捌きや手の内などの説明を理解し自分のものとしましょう。
以上品川稽古の報告です。
9月4日(木) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
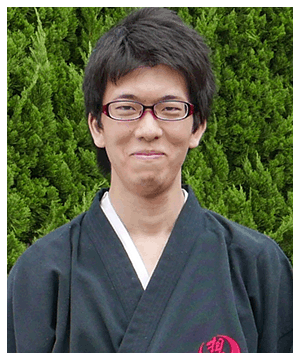 節目という語源は竹にあるようです。そこから転じて、重要な物事の区切りをさすとのことでした。
節目という語源は竹にあるようです。そこから転じて、重要な物事の区切りをさすとのことでした。
この日に行いました腹抜きの動作について、抜刀時に切っ先を鯉口付近に少々残すこと、というのは節目に当たります。そこから、足を差出すことで自然と刀の先が相手の喉元に伸びていく。あるいは正眼へ誠に自然と収まる。いずれも私の好きな動作です。非常に難しいですが。
さて、「抜刀時に切っ先を鯉口付近に残す」ということについては、何卒省略せぬようにお願いします。冒頭で話した節目です。稽古を重ねた方においては、動作が早すぎてほんの一瞬のこととなるでしょうが、そこに切っ先がしかと乗っているか否かは自身が一番わかると思います。なお、初心者の方はこれをかなり厳格にやっておられます。その姿を見て、私も自身の動作を見直しました。
そんな節目を意識しながらの腹抜きの稽古でした。実施した形は左月、胸尽くし、響返しです。腹抜きですので鞘を傷めないように気を付けたいところです。当たり前ですが、刀は鞘に沿って抜けます。鞘の角度に対して直角には抜刀できません。身体の運用で、鞘にも刀にも自分自身にも無理がないように致しましょう。
本日より当稽古場は木曜日に実施しております。変わらず参加して頂ける方々に感謝です。次の稽古も一緒に頑張っていきましょう。
8月31日、9月4日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *31日(日)基本稽古後リクエストにより胸尽くしの腹抜きを何度も繰り返しました。
*31日(日)基本稽古後リクエストにより胸尽くしの腹抜きを何度も繰り返しました。
膝を緩め後方に重心を移動しつつ右半身を開き体捌きと鞘引きにより抜刀しますが鞘を傷めぬ様、初めは鞘付き木刀で感覚を掴んで貰った後、居合刀で稽古しました。
*4日(木)基本稽古後は腹抜きをテーマに「胸尽くし」「左月」「神妙剣」の形稽古をしました。
アメリカは9月1日「労働者の日」(Labor Day)連邦の祝日で、この日は夏の終わりを告げる意味もあり友達や家族と3連休を週末旅行やBBQなどをして祝います。
最近セドナの朝は気温16度〜18度と過ごし易く秋の気配も感じます。
8月31日(日) 池袋・剣術:関戸光賀
 小太刀の稽古を久しぶりに再開しました。
小太刀の稽古を久しぶりに再開しました。
形を五本通して行いましたが、動きにブランクはまったく感じませんでした。
稽古というものは、重ねれば重ねるほど、まるで貯金のように体に武道的な動きが蓄えられていくものなのですね。
ただし、間違った動きを身につけてしまうと、それを修正するのは大変です。教える側にとっても同じことです。
どうか、くれぐれも頑固にならず、素直な心で稽古に臨んでください。
8月31日(日) 品川・居合:大隅幸一 師範
 8月最終日の稽古となりました。
8月最終日の稽古となりました。
まだ猛暑日が続いていますが稽古場は空調を調節して快適な環境で稽古しております。
本日は特に鞘引きを意識して稽古していただきました。
居合では鞘引きが重要な動作になります。
鞘引きをしっかり行うことで、刀を素早く無理なく抜いたり鞘から離れた刀の物打ちを敵の斬るべくところに向かうようにできます。
また本日の稽古でも鞘鳴りが減っておりましたので鞘も傷めない利点もあったと思います。
今後も大事な鞘引きを意識して稽古してまいりましょう。
8月30日(土) 赤羽・居合:宮澤和敬 師範代
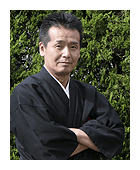 外気の体感温度は40°Cを超える酷暑でしたが、稽古場の冷房を効かせて会員の皆さんの到着を準備万端で待っていました。
外気の体感温度は40°Cを超える酷暑でしたが、稽古場の冷房を効かせて会員の皆さんの到着を準備万端で待っていました。
仕事の関係で新春稽古以来、稽古を休まれていた浅野指導補が8ヶ月振りに元気な姿を見せてくれました。演武会へ参加出来るとの話で城北居想会にとって浅野指導補の復帰は、何より喜ばしい出来事でした。
本日は手順の入っている会員さんの参加だった為、各自で課題を考えていただきながら刀を多く振っていただくことにしました。
基本稽古に続き、形稽古は「真」「本腰」「響返し」「胸尽し」「両車」「玉光」「前腰」「神妙剣」「右の敵」を行いました。
素振り稽古が終わった頃に年配の会員さんから体調不良の申し出があり、軽い熱中症の症状だと推察しました。
すぐに横になっていただくと同時に熱中症対策の塩タブレットとドリンクを補給していただき、冷却タオルで首周りや身体を冷やしながら扇風機を使用して火照った身体を冷やす措置を行いました。
終わり時間10分前には体調がすっかり回復し、帯刀せずに軽く身体を動かせる程度まで良くなり、安心しました。
稽古場まで暑い中、歩いて来られると思うので、冷房が効いている稽古場でも決してムリすることなく、体調の変化を感じた時点で早めに休息を取っていただくことがとても大切なことです。
今後も安全第一に稽古していきたいと思います。
8月30日(土) 田町・居合:山名宗孝 指導員
 土曜日の田町稽古では、腹抜きの形から左月、胸尽し、縦抜きの形の陰中陰を稽古しました。
土曜日の田町稽古では、腹抜きの形から左月、胸尽し、縦抜きの形の陰中陰を稽古しました。
入会されて間もない方は腹抜きも、座技での抜刀や転身も難しく感じられると思います。体の使い方もそうですが、刀を体の延長線の様に扱いたいです。
ところで私がご指摘を頂くところである「力み」や「呼吸」について少しずつ考えるようになりました。
居合の稽古では自分のタイミングで動けるので気が付きにくいのですが、抜刀の際など息を止めていることがありませんか?
筋力やフィジカルの強さは往々にして有利に働きますので、それを否定できないですが、「力むこと」が常在化した場合、反応の遅さや持久力の低さなど、臨機応変な対応が困難です。
どういう居合を目指すのか、時々自問自答しながら稽古を重ねて行きたいですね。
8月24日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
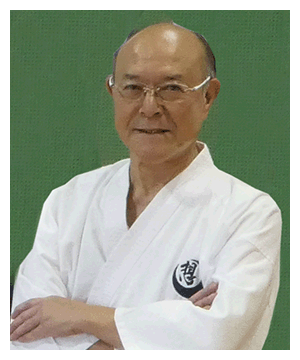 今日も朝早くから暑い一日のはじまりです。
今日も朝早くから暑い一日のはじまりです。
日ごと今までにない暑さを更新していますが、毎朝のウォーキングの時、2~3日前からツクツクボウシが鳴き始めました。気温に関係なく例年と同じ時期に鳴き始めています。今まではツクツクボウシの鳴き声を聞くと、もうすぐ夏が終わり秋に近づく頃と思っていましたが、予報によれば今年はこの暑さは
11月まで続きそうだとか・・・
この暑さの中、市川の稽古場にいつもの会員さんが参加されました。
基本稽古では、腕だけに頼らず半身を意識して身体全体を使った斬りと刃筋(特に横一文字)、斬り終わりに切先を飛ばさないよう確認しながら稽古を進めました。
基本の一、二では稽古場の端から端まで、各自目標を定め真っすぐに斬り進むこと、斬り終わりに左足かかとが大きく浮かないよう意識していただきました。
形稽古は、向抜、円要、陰中陽、夢想返し
向抜、円要、夢想返しについては股関節の緩みを使った縦の動きでの転身、陰中陽では正中線を外して敵の斬りを受け流すための鎬の位置と足捌きにポイントを置きました。
8月24日(日) 田町・剣法:宮澤和敬 師範代
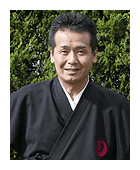 いつもの手順で素振り、受け流し、廻剣、上段と下段からの付けなど基本稽古を行いました。重心を低く保ちながら軸をしっかり立て、気剣体一致するように稽古しました。
いつもの手順で素振り、受け流し、廻剣、上段と下段からの付けなど基本稽古を行いました。重心を低く保ちながら軸をしっかり立て、気剣体一致するように稽古しました。
袈裟斬りの4本打ち込みでは正中線を意識する動きによって腕力ではなく、半身の切り返しによる身体全体の動きで剣に力を乗せるように打ち込んでいただきました。
形稽古は十剣秘訣の一本目である獅王剣の動きを確認しました。単純に形の手順通り動くのではなく、この形は間合と呼吸の読み合いが大切となるので、この点を意識していただきながら稽古しました。
棒稽古でも正中線から棒の位置を動かさず、半身から半身の動きに注意しながら稽古を行いました。
本日も皆さんの気力が充実し、身体もしっかり動けたと思います。
8月24日(日) 田町・居合:五島博 師範
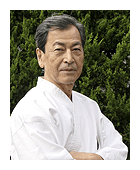 朝から猛暑日を予感させる暑い日でした。
朝から猛暑日を予感させる暑い日でした。
今日は特に抜刀及び納刀時の左半身の使い方に注力して基本の一二及び形稽古をするように伝えました。抜くも納めるも左からと云われるように左手(左半身)は居合の体捌きで大切になります、左半身による力強い鞘引きは抜刀時の剣尖の冴をうみ又、鞘引きにより左半身と対応する右半身が前に出ることで仮想敵に届き両手による敵の打ち込みの間合に対して片手の有利になります。
左手(左半身)を上手に使って演武をする事を意識して稽古を継続しましょう。
8月21日、24日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *21日(木)手首を使わない、切先を敵に外さない、手の内は柔らかく、軸のブレを無くす事を確認しながら基本稽古を進めました。
*21日(木)手首を使わない、切先を敵に外さない、手の内は柔らかく、軸のブレを無くす事を確認しながら基本稽古を進めました。
「左月」では左足の親指と右の膝を支点として左の敵に軸を立て向き直る動きを繰り返し、同様に「右」も身体の回転を確認しました。
胸尽しの抜刀を稽古した後、五応を稽古しました。
*24日(日)右半身、左半身の動き及び緩みと正中線、刀と身体が等速で同時に動かす意識を持って五用及び前回に引き続き胸尽くしの抜刀、左月の腹抜きを繰り返し稽古しました。
宗家の稽古日記で記された刀礼について詳しく解説下さいましたので、稽古を開始する前、皆さんに読みお伝へさせて頂きました。
改めて刀礼の奥深さを知ると同時に大切さを学び、皆で気持ちを込めて刀礼を致しました。
8月22日(金) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
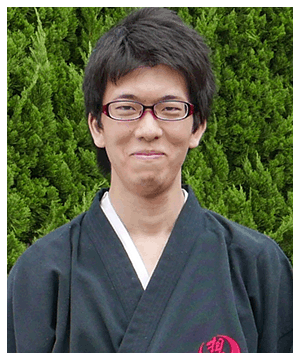 前回の稽古に引き続き、座技を稽古しております。この日は五箇を行いましたが、初心のうちは複雑な動きが多くて大変かと思います。焦ることなく、一つずつ覚えていきましょう。
前回の稽古に引き続き、座技を稽古しております。この日は五箇を行いましたが、初心のうちは複雑な動きが多くて大変かと思います。焦ることなく、一つずつ覚えていきましょう。
やはり座りの方が体は動かしにくいです。その上、相手は立っておりますので絶望的に不利です。敢えてそんな状態で、如何に隙なく刀を振るか。体を壊さない程度に色々動いてみながら、一緒に稽古を積み重ねていきましょう。
説明の備忘録を記しておきます。
・水月…刀の高さを意識するように
・響返…構え直しで刀が正中線を外れないように
次回には違う課題にぶつかっていけるよう、引き続き共に頑張りましょう。
8月17日(日) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
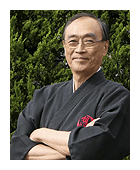 本日は入会希望の方の見学がありました。20代の好青年。
本日は入会希望の方の見学がありました。20代の好青年。
居合や剣法、古武道についてのことや一般稽古の流れ、会の年間のイベントなどについて聞いてもらいながらですが、稽古の様子を終始興味深く見学されていました。
机に向かってコンピューターとにらめっこの時間がながい仕事で運動不足になりがち、何かしら運動をしたいということ、日本の古武道、居合や刀に興味があったことで始めようと思ったことが動機とのことでした。
私が始めたころは想像していたことと違ったということも多く、上手く出来ないことで戸惑うことも度々でしたが、何度か稽古をするうちに出来なかったことが出来るようになることで面白くなってきたように記憶しています。稽古を重ねるうちに、また新たな課題が出てきて迷うことのくり返しでしたが、稽古の時間そのものが楽しくなってきたようにも思います。
古武道に限らないと思いますが、指導的立場のものも初心の方や年代の違う方との稽古で新たな気付きや学ぶことが少なからずあると感じて思います。一緒に楽しく稽古出来ればと思います。
8月17日(日) 秋葉原・居合:関戸光賀
 お盆の期間にもかかわらず、無級から有傳者まで多くの方々が居合の稽古に参加され、充実したひとときを共有することができました。
お盆の期間にもかかわらず、無級から有傳者まで多くの方々が居合の稽古に参加され、充実したひとときを共有することができました。
さて、ここからは稽古の内容から少し離れ、刀礼についての思いを記したいと思います。
刀礼とは、文字どおり刀に対する礼であると同時に、刀を通して古人へ敬意を表する行為でもあると考えられます。
ここでいう古人とは、ご先祖や流派を興し、今日までその教えを伝えてくださった多くの先人を指し、その御霊に感謝を捧げる所作でもあります。
さらに、刀礼のひとときは、日常から非日常へと身を移す「結界」を越える行為であり、己の心を鎮め、居合の稽古に臨むための大切な準備でもあるでしょう。
体の軸が取りづらい日もあれば、刀を置く位置が定まらない日もあり、同じ所作であってもそのときどきで違いが感じられます。
刀礼には、その日の心身の状態が自然と映し出されているのではないでしょうか。
8月16日(土) 池袋・居合:宮澤和敬 師範代
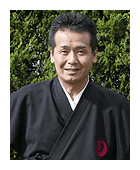 お盆休み中ですが、稽古熱心な会員さんが参加されて居合稽古を行いました。
お盆休み中ですが、稽古熱心な会員さんが参加されて居合稽古を行いました。
本日は前面が鏡張りになっている池袋Biz稽古場であり、1人あたりのスペースも十分に確保できた為、鏡に写るご自身の正中線や軸を確認しながら基本稽古を丁寧に行いました。
級、傅位に関係なく知らず知らずのうちに自分の癖というものができてしまいます。
真っ直ぐ構えているつもりだけど左右にズレていたり、切っ先が少し下がっていたり、刀を身体の中心で取れていなかったり…等、確認することは多くあります。
自分では出来ていると思っているので、この癖に気付くには客観的に見てもらって指摘されるか、鏡に写った自分自身の姿を確認することが有効です。
鏡がある稽古場でスペースがある場合は、自分は出来ているという慢心の気持ちを捨て、前後左右に写る自分自身の姿をしっかり確認して、修正していくことが居合では大切です。
8月16日(土) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
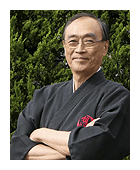 本日は、基本御素振り、抜刀の稽古に少し時間を多く裂いて稽古しました。
本日は、基本御素振り、抜刀の稽古に少し時間を多く裂いて稽古しました。
緩みから始まる体の動き、切り終わりの体勢等出来るだけ自然な形を意識してもらっています。
基本の一、基本の二では左右交互に半身を切って前進しますが、軸を意識して股関節の緩みで半身を切らないと、敵を捉えて前に出す足(爪先)が内側に入り真半身に近い動きになりがちです。左右の足と真ん中の正中線の軸の三つの軸を意識してみてください。その軸が重ならないように股関節の緩みを使って三つの軸が並行のまま半身をきって前進する動きにしたいものです。三つの軸を意識するとご自身の動きに違和感があるかもしれませんが、それはその動き自体がどこか不自然な形になっていることかもしれません。体のねじれなどで上手く動けないような感じの時などは、三つの軸を意識して稽古するのも一つの方法かもしれません。
8月10日(日) 田町・剣法:関戸光賀
 本日の稽古では、お隣の半面を大隅師範が居合、もう半面では私が剣法を担当しました。
本日の稽古では、お隣の半面を大隅師範が居合、もう半面では私が剣法を担当しました。
稽古場は畳でしたので、今回は居合と剣法における「畳での稽古の効果」について考えてみます。
畳は床と比べて足裏が滑りにくく、わずかに沈み込むため、動きをスムーズにするには膝の緩みを活かし、丁寧な重心移動を心がける必要があります。
その結果、体幹が鍛えられ、姿勢を正す効果も期待できます。
畳ならではの稽古の感覚を活かしつつ、床でも畳でも同じ動きができるよう、日々の稽古に励みましょう。
8月10日(日) 田町・居合:大隅幸一 師範
 立秋も過ぎて久しぶりの雨で暑さも少し和らいだ稽古日でした。
立秋も過ぎて久しぶりの雨で暑さも少し和らいだ稽古日でした。
本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
今回も注意点のポイントを絞って稽古していただきました。
基本稽古では、爪先を回さないで敵に真っ直ぐ向けて中心を軸にして動くことに気を付けて稽古してもらいました。
形稽古では、向抜きは一刀目で左爪先を内側に巻き込まないようにし反転時に右足をしっかり捌いて斬ること、胸尽しは腹抜きを遠回りせず腹に寄せて一つで抜くこと、水月では横一文字からの緩みは切っ先を支点にして緩むようにすること、野送りでは受けの形で敵の斬りに対し自分の頭を守れる位置に刀をもっていくことに特に注意していただきました。
居合は剣法と違い実際の相手がいないので難しいですが少しずつでも敵を意識して稽古してみましょう。
8月9日(土) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
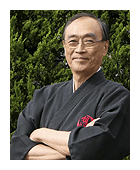 一つ一つの動作を確認して丁寧に精度を高めるように意識しての稽古。
一つ一つの動作を確認して丁寧に精度を高めるように意識しての稽古。
技量レベルが上がれば動きも変ると同時に注力する事柄も変わってきます。初心の時期は正しい動き(かたち)を習うところから始まりますが、技量が上がってくればそのレベルに応じて力ではなく緩みをうまくコントロールしての動作を求められます。目標とするところはやはり正しい形、精度の高い演武です。
理合いを知り正しい動作を意識して、繰り返し稽古することで、シンプルでメリハリのある理にかなった動きに少しずつでも近づければと思います。
8月9日(土) 赤羽・居合:中野瑞岳 指導補
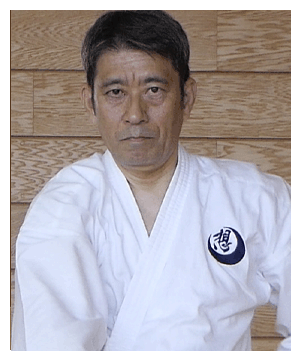 稽古は、何度も何度も反復して行います。直ぐに出来るなら良いですが中々上手く出来ない事が多いですね。
稽古は、何度も何度も反復して行います。直ぐに出来るなら良いですが中々上手く出来ない事が多いですね。
最初は何が出来てないのかも分からない位かもしれません。
しかし何度も繰り返す事でしばらくすると見えてくるものも有ります。
辛抱強く試行錯誤を続けていると、ある時そうなのかな?とか徐々にこういう事かな?と思う時が出て来ます。一つ一つ殻が割れて中身が徐々に見えて来たり、今まで点と点で感じていた事が線で繋がって見えて来たりする時があります。
私はまだまだ未熟な者でその様なときが現れるのが少ないのですが、これが気づきなのかも知れません。
これからもご一緒に見えて来るものを探しに稽古を行いましょう。
8月8日(金) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
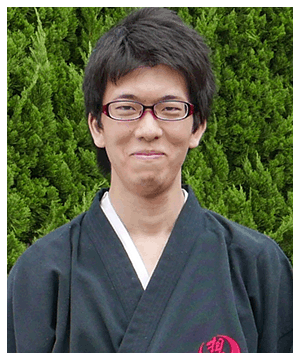 五用を通しで稽古致しました。形は回数を積み重ねればそのうち覚えていきますが、それだけの稽古では間の取り方や集中の持続を培うことがなかなか厳しいと思います。折を見て、また通しの稽古を行いますので、此方に参加される方におかれましては他の稽古場などでも指導者から形をよく学んでみて下さい。手順を覚え、気を途切れさせずに通しで稽古が行えるよう目指してみましょう。
五用を通しで稽古致しました。形は回数を積み重ねればそのうち覚えていきますが、それだけの稽古では間の取り方や集中の持続を培うことがなかなか厳しいと思います。折を見て、また通しの稽古を行いますので、此方に参加される方におかれましては他の稽古場などでも指導者から形をよく学んでみて下さい。手順を覚え、気を途切れさせずに通しで稽古が行えるよう目指してみましょう。
形の細かい説明をしていなかったので此方にて補足を致します。
向抜は前後の敵に対する形です。反転の際に刀の切先が正中線から逸れないようにしましょう。手の内の緩みが肝です。
初めのうちは刀の切先を逐次確認しながら、反転の動作だけを稽古すると良いでしょう。その際、膝が痛くなければ座りで稽古をなさることをおすすめ致します。下半身の動きが制御される分より困難になりますが、その分良い稽古になります。
8月9日(土) 田町・居合:髙橋武風 指導補
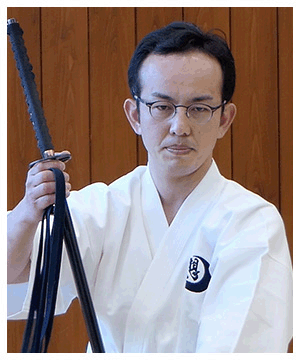 先週、昇級昇傳審査が実施されました。
先週、昇級昇傳審査が実施されました。
審査合格された方、おめでとう御座います。
稽古を続けていると、気になる点が二つ三つ四つと沢山出て来ると思います。
全部同時に気にしてしまうと更に分からなくなってしまうと思います。
その時はどれか一つに集中して修正してみましょう。
以外と一つの修正した事により他も良くなる事があります。
まだまだ暑い日が続きますが、体調には気をつけて稽古を続けて参りましょう。
8月3日、7日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *3日(日)H.Y.さんアラスカでの仕事を終え、7週間振りにご夫妻揃っての稽古日でした。
*3日(日)H.Y.さんアラスカでの仕事を終え、7週間振りにご夫妻揃っての稽古日でした。
基本の一、二を重点的に改めて正しい振りかぶりと斬りの確認をした後、形は五用、五応を稽古しました。
*7日(木)形の漢字、書き順のアプリをスマホで参照確認しながら五箇、走り懸りの形8本を稽古しました。
最近のアプリは非常に分かり易く便利になりL.O.さんの形の漢字の精度も、形の精度も上達が見られました。
基本の一、二を稽古する上で宗家がアップされたYouTube動画で「居合を学ぶ#01振りかぶり」を参考にさせて頂き稽古しました。
8月3日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
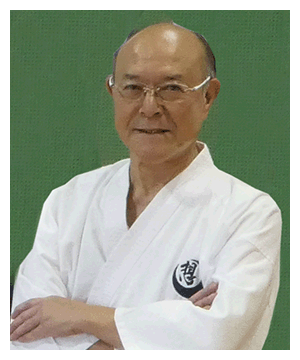 タイ駐在のUさんが一時帰国されており本日の稽古に参加されました。
タイ駐在のUさんが一時帰国されており本日の稽古に参加されました。
市川では先週、形稽古18形を終え今回から五用、五応、五箇、走り懸りの最初の形、真、胸尽し、水月、前腰からスタートです。
毎回各形を横串で順繰りに稽古していますが、その都度各形のポイントとなる所作を繰り返すことにより、正しい所作が身についてくると思います。
また、ただ漠然と稽古するのではなく、そういう意識をもって稽古を続けていけば自ずと技量は上がってくるものと思います。
とにかく、古武道というものを楽しみながら稽古を続けていきましょう。
8月2日(土) 滝野川・居合:三浦無斎師範代
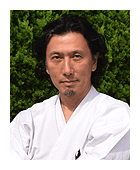 明日の審査を受けられる方が4名いらっしゃったので、形稽古を中心に行いました。
明日の審査を受けられる方が4名いらっしゃったので、形稽古を中心に行いました。
審査を受けられる方の気合が稽古場に蔓延しており、参加者全員が良い刺激を受け取ったのではないかと思います。
審査にせよ、演武会にせよ、何らかの目標が出来ると、集中力が
高まり、さらに技量が上がると思います。
秋に向けて、ご自身の課題を見つけて取り組んでみましょう。
さらなる高みを目指して共に精進して参りましょう。
8月2日(土) 田町・居合:山名宗孝 指導員
 11月8日に演武会を行います。
11月8日に演武会を行います。
上達の機会となるよう、皆様予定を調整して参加しましょう。
本日は形と形の繋がりの所作に注意して頂きました。形と形の間の転身やふとした動作など、何気ない所作が美しく落ち着いて見えると、その方の重ねて来られたものが見えるように思います。
演武会は緊張すると思います。普段何気ない所作もガチガチになるかもしれません。演武会に向けて普段の所作も見直しては如何でしょうか?
ページトップへ
7月29日(火) 水道橋・剣術:関戸光賀
 日頃「打太刀は、仕太刀の良いところを引き出すように」と言っていますが、今日はあえてその逆のことをやってみました。
日頃「打太刀は、仕太刀の良いところを引き出すように」と言っていますが、今日はあえてその逆のことをやってみました。
つまり、「打太刀は、仕太刀の打が甘ければ、取っていっても構わない」と。
この形では、相手の剣を打ち落とすタイミングが少しでもずれると成り立たたないことが実感できました。
またそれ以外にも、多くの学びがありました。 こうした稽古ができるのも、みなさんがそれぞれ自分の動きをしっかりコントロールできているからだと思います。
7月24日、27日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *24日(木)居合18形の漢字の書き順と画数も確認しながら稽古しました。
*24日(木)居合18形の漢字の書き順と画数も確認しながら稽古しました。
L.O.さんは一部の書き順の確認はしたものの、形の手順及び漢字も全て覚えられましたので、形の動作精度をあげるのと同時にこれからは日本文化をより深く理解してもらう為にも漢字の左右バランスと力を抜く所、力を入れる所も同時練習致します。
*27日(日)形はS.Y.さんのリクエストで水月と響返しを行った後、五用、五応の稽古を剣体一致の動きを心掛け出来る限りゆっくりと振ってもらい、速く振って見過ごされる幾つかの修正点に気づいてもらいました。
7月27日(日) 田町・剣術:関戸光賀
 剣術の稽古は、居合と異なり一人稽古ではありませんので、相手によって打つ位置や間合いが変わってきます。
剣術の稽古は、居合と異なり一人稽古ではありませんので、相手によって打つ位置や間合いが変わってきます。
その変化に身体が対応できるよう、日々稽古を重ねていきます。
また、相手の良いところを引き出してあげるのが打太刀のお仕事だと思います。仕太刀が動きやすく、上手くなったと感じてもらえるような、そんな巧みさを目指していきたいと思います。
7月27日(日) 田町・居合:和田冠玄 指導員
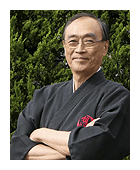 本日の稽古では初心者から傳以上の方まで技量レベル差の大きい参加者での稽古でした。初心の方は高位の方の演武を見て動きをよく見て習おうとします。稽古指導でも見て真似るところから形を覚えてもらうということもあります。そんな中で気を付けたいのは上位者の速さについていこうとして、ついつい早さを求めてしまうことです。早い動作で出来ているように思うことも多々あります。出来ているようでも不正確な動きでは上達は遅くなると思います。
本日の稽古では初心者から傳以上の方まで技量レベル差の大きい参加者での稽古でした。初心の方は高位の方の演武を見て動きをよく見て習おうとします。稽古指導でも見て真似るところから形を覚えてもらうということもあります。そんな中で気を付けたいのは上位者の速さについていこうとして、ついつい早さを求めてしまうことです。早い動作で出来ているように思うことも多々あります。出来ているようでも不正確な動きでは上達は遅くなると思います。
要所で正しい動き、形を意識してゆっくり繰り返し稽古することが逆に早道になると思います。ご自身の技量レベルに合わせてスピードではなく一つ一つの動作の精度を上げることに気を付けて稽古してみましょう。
7月25日(金) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
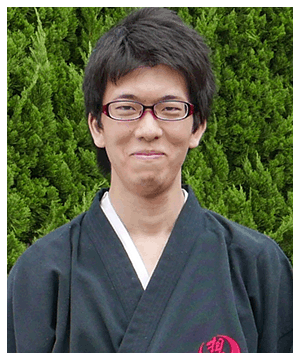 剣術の稽古は、居合と異なり一人稽古ではありませんので、相手によって打つ位置や間合いが変わってきます。
剣術の稽古は、居合と異なり一人稽古ではありませんので、相手によって打つ位置や間合いが変わってきます。
その変化に身体が対応できるよう、日々稽古を重ねていきます。
また、相手の良いところを引き出してあげるのが打太刀のお仕事だと思います。仕太刀が動きやすく、上手くなったと感じてもらえるような、そんな巧みさを目指していきたいと思います。
7月20日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 基本稽古の前に股関節周りの背骨から大腿骨を繋ぐインナーマッスルである唯一の腸腰筋を働かせる為に片足立を取り入れ体のバランスを整えました。
基本稽古の前に股関節周りの背骨から大腿骨を繋ぐインナーマッスルである唯一の腸腰筋を働かせる為に片足立を取り入れ体のバランスを整えました。
形稽古では刀の操作法と体の使い方を中心に両車、夢想返しでは後方の敵を斬る体捌きと手の内を繰り返し稽古した後、破図味を除く五箇と四方を除く走り懸りを通しで行いました。
居想無外流は、無駄の無い動きが魅力でもあり、それを習得する為に長い道程を一歩ずつ進んで行きたいと思っております。
7月20日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
 梅雨明けとともに朝から暑い一日となりました。
梅雨明けとともに朝から暑い一日となりました。
本日は無級から傳位までほぼいつもの方々が参加され、暑さ対策としてこまめに給水しながら稽古を進めました。
基本稽古では、刀を真ん中で取ること、鞘をしっかり引いての抜刀、真っ向斬りでは左腕を伸ばして前の敵を斬ること、剣体一致の動きなどいつもの注意点を確認しながら稽古しました。
形稽古は、左月、両車、陽中陰、神妙剣
左月、神妙剣に対しては、事前に基本稽古時腹抜きを多めに稽古しましたが、
転身を伴う動きのため稽古回数の少ない方にとっては難しいようでした。
まずは各形の正しい所作を覚えて、自然に体が動くように回数多くこなしていきましょう。
7月19日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
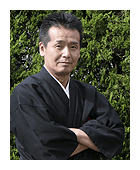 朝から晴天で汗ばむ暑さだったので、開場と共に冷房とサーキュレーターを動かし、会員の皆さんが来る頃には快適な環境になっていました。
朝から晴天で汗ばむ暑さだったので、開場と共に冷房とサーキュレーターを動かし、会員の皆さんが来る頃には快適な環境になっていました。
本日は傅位者から一般稽古2回目となる新人まで幅広い参加者がいたので「刀を真っ直ぐに振る」というシンプルなテーマで稽古を行いました。
真っ向斬りを正中線に沿って真っ直ぐ振ることは、単純で簡単そうに思いますが、実は奥深いことです。技量に応じて真っ向斬りの誤魔化しがきかない難しさを感じてもらえたと思います。
最後に全員で刀礼を行い、一つ一つの細かい動き、指先の所作など確認しました。初心者に限らず、知らず知らずのうちに基本と違った動きや無意識の癖になっていることもあるので基本所作の再確認を行いました。
「自分は出来ている」と過信せず、出来ていない自分と向き合うことが上達に向けた一歩となります。
7月19日(土) 田町・居合:大隅幸一 師範
 梅雨明けで暑さが戻ってきましたので引き続き熱中症に気を付けて稽古するようにしました。
梅雨明けで暑さが戻ってきましたので引き続き熱中症に気を付けて稽古するようにしました。
本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
本日の稽古ではポイントを1・2点に絞って注意していただきました。
基本稽古では、丁寧に基本を大事に動いてもらいました。
形稽古では、真では軸を立てて動くこと、胸尽しでは腹抜きを遠回りせず腹に寄せて一つで抜くこと、水月では横一文字からの緩みを棒立ちや緩みすぎにならないこと、玉光では縦抜きを右手だけで抜かず左の股関節と膝の緩みを使うことに特に注意していただきました。
私も注意し直す点は沢山あって注意散漫になりがちですが、一度に何もかもを出来るようにすることは難しいので、一つひとつでも出来るように心掛けるよう意識していこうと思っています。
焦らず急がず着実にの精神で稽古に励んでいきたいです。
7月13日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 目線を含めての動作、所作を大事に刀礼、基本、形稽古する際、細かい点に注意を払い稽古をしました。
目線を含めての動作、所作を大事に刀礼、基本、形稽古する際、細かい点に注意を払い稽古をしました。
気づいた時に基本に戻り少しずつでも前進出来ればと思います。
S.Y.さんより稽古前の刀礼で現実世界からサムライの時代へタイムスリップし稽古後の刀礼で現実に戻る感覚、平生の仕事や関わりから離れ無心で稽古に専念する2時間を楽しんでいますとのコメントをもらい私も同感しました。
7月12日(土) 田町・居合:関戸光賀
 剣法の稽古では、居合と違って相手がいますので、互いの呼吸を合わせることが大切です。
剣法の稽古では、居合と違って相手がいますので、互いの呼吸を合わせることが大切です。
とはいえ、言葉にするのは簡単でも、実際にはなかなか難しいものです。
上位者は、技量の差はもちろん、体格や性別といった点にも配慮しなければなりません。
稽古では次々に相手が変わるため、その都度、瞬時に対応する判断力が求められます。
つまり、剣法の稽古では、身体だけでなく頭も大いに使うのです。
一方、初心者は技や形を頭で考えるよりも、まず体で覚えていくことが大事です。
だから、できるようになるまでには時間がかかります。
焦らず、ゆっくり覚えていきましょう。
7月12日(土) 赤羽・居合:中野瑞岳 指導補
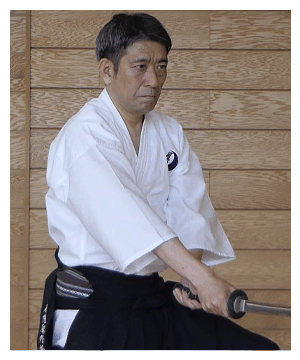 明鏡止水
明鏡止水
先日、NHKの明鏡止水が放映されてました。視聴されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。岡田准一が司会で武術について色々な視点で紹介している番組です。
今回は武術とスポーツの共通点というテーマで大谷選手を侍として取り上げ野球を武術の視点からみていく内容でした。
特に印象的だった所は、連動と手の内という話で、稽古で耳にする剣体一致、半身、軸を建てる、手の内股関節の緩みなど共通している部分が随所にあり改めて基本が大切なのだと思いました。
野球という違った視点でみていくことで体系的に整理がついてより奥深さを感じる事が出来ました。
物事はそうですが一つの視点で探求する事と複眼的な視点と両方で観る目が必要なのでしょう。
またご一緒に稽古を行いましょう。
7月12日(土) 品川・居合:田澤尊伯 指導補
 稽古の合間に「一度なくなった梅雨前線がまた、戻ってきたらしい」などと会話をしていました。その後、調べたところ、どうやら、関東の梅雨入りと明けは、例年並みの予想のようです。
稽古の合間に「一度なくなった梅雨前線がまた、戻ってきたらしい」などと会話をしていました。その後、調べたところ、どうやら、関東の梅雨入りと明けは、例年並みの予想のようです。
何となく、実感とずれている気もしていますが、いずれにしろ、季節の変わり目ですので、体調に気を配りつつ、稽古をしていきたいですね。
さて、本日は、各自のペースで取り組めるように配分しつつ、一部、希望する形をお聞きして、稽古しました。共通して、軸を立てることおよび、剣体一致について留意頂きました。
8月の審査に向けて、補習や自主稽古に取り組む方たちもおり、それぞれに熱心に取り組まれておりました。
引き続き、ご一緒に稽古を重ねて行きましょう。
7月11日(金) 西新宿・居合:小井 健熙 指導員
 私の嗜好ですが、音の少ない稽古場が好きです。そのため、私が担当する場では足音も掛け声も立たせず、少々煩わしく思われるくらい鞘の音を指摘させて頂いております。そのため、施設の方から「武道なのに本当に静かで、何もしてないかと思って様子を見に行ったことがあります。でも、皆様集中してしっかりやっておられますね」と。どうやら剣道のようなものを想像していたようです。ともあれ、当稽古場に参加して頂く方の技量のおかげで、誠に良い印象で施設を使うことができております。ありがとうございます。
私の嗜好ですが、音の少ない稽古場が好きです。そのため、私が担当する場では足音も掛け声も立たせず、少々煩わしく思われるくらい鞘の音を指摘させて頂いております。そのため、施設の方から「武道なのに本当に静かで、何もしてないかと思って様子を見に行ったことがあります。でも、皆様集中してしっかりやっておられますね」と。どうやら剣道のようなものを想像していたようです。ともあれ、当稽古場に参加して頂く方の技量のおかげで、誠に良い印象で施設を使うことができております。ありがとうございます。
本日は傳位者のみの参加でした。審査も近いので形を多めに稽古しましたが、傳位ともなると最早私から言うこともございません。その中でも敢えて申し上げたことは、身体に無理の無いように、という毎度の話でした。既に稽古で形を繰り返し行なっているかと思いますが、蓄積された無理のある動きによって身体を故障させないようご留意下さい。
実施した形は向抜、陽中陰、夢想返し、神妙剣でした。相変わらず教本に立ち返りつつの稽古ですが、必要なことは全て書いてあります。動きに悩んだ際は是非ご参照を。
7月6日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 腕・体・足の動きの一致、所謂「剣体一致」と股関節を使い膝を緩めながら重心の位置に気を付け敵対動作を意識し居合を通しての体の使い方に慣れるのは実に奥が深いです。
腕・体・足の動きの一致、所謂「剣体一致」と股関節を使い膝を緩めながら重心の位置に気を付け敵対動作を意識し居合を通しての体の使い方に慣れるのは実に奥が深いです。
これらを意識しながら腹抜きの形、左月・胸尽し・神妙剣、縦抜きで向抜・玉光・夢想返しを繰り返し稽古しました。
セドナは星空保護区(ダークスカイ・コミュニティー)として世界で8番目に選ばれた都市です。
本日の七夕は天の川、北斗七星、満天の星空を見上げ心を整えたいと思っております。
7月6日(日) 品川・居合:関戸光賀
 体の軸がまっすぐに立ち、捻れやうねりがなく、意識と体が常に相手の正中をとらえていれば、居合としては十分に上手といえるでしょう。
体の軸がまっすぐに立ち、捻れやうねりがなく、意識と体が常に相手の正中をとらえていれば、居合としては十分に上手といえるでしょう。
それに加えるなら、所作の美しさです。
その美しさは、相手への礼の心と、無駄を削ぎ落とした動きから生まれるものだと思います。
7月5日(土) 田町・居合:関戸光賀
 無外流居合の動き出しは「一呼吸半」と言われます。
無外流居合の動き出しは「一呼吸半」と言われます。
本来これは、禅において歩き方を示す際に用いられる言葉ですが、居合においても、一呼吸半を置いてから動き出すことで、心の雑念が薄まり、また息を吐きながら動くため、力強さが生まれます。まさに居合にちょうどよい間(ま)といえるでしょう。
ただし、級位まではこの「一呼吸半」を意識して稽古することが望ましいですが、有傳者に至っては、体が命じたときに自然と動き出すような境地を目指しましょう。
敵に悟られないように動く。これも極意のひとつかと思います。
7月5日(土) 田町・居合:髙橋武風 指導補
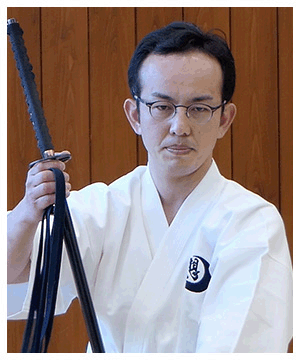 今日も気温、湿度高くたっているだけで汗だくになりました。
今日も気温、湿度高くたっているだけで汗だくになりました。
水分補給多めに稽古を行いました。梅雨はいったい何処へ。
昇級昇傳審査の受付が始まっています。
審査は非常に緊張しますが、その緊張感がとても良い稽古になります。
また、いつもより細かく動きについて気にするので上達につながるかと思います。
是非挑戦してみては如何でしょうか。
柔らかな動きは構えだけでなく、抜刀時においても大切なポイントです。鞘から刀を早く抜く為には無駄な力を入れず、瞬発的な力を使って抜く必要があります。
柔らかく靭やかな筋力を使えるように稽古していきましょう。
7月5日(土) 赤羽・居合:宮澤和敬 師範代
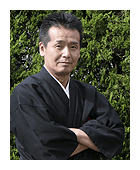 本日は先週の稽古に引き続き、軸をしっかり立てること、身体の力を抜き柔らかく構えることを意識していただきました。
本日は先週の稽古に引き続き、軸をしっかり立てること、身体の力を抜き柔らかく構えることを意識していただきました。
首を背骨の上へしっかり置いて乗せるイメージで軸を立てたうえ、刀を振り被った時に上半身の力を抜いて柔らかく構えて刃筋がしっかり通るように刀を振っていただきました。
柔らかな動きは構えだけでなく、抜刀時においても大切なポイントです。鞘から刀を早く抜く為には無駄な力を入れず、瞬発的な力を使って抜く必要があります。
柔らかく靭やかな筋力を使えるように稽古していきましょう。
7月5日(土) 品川・居合:大隅幸一 師範
 今日も気温が高く蒸し暑い日ですが稽古場は空調を調節して快適な環境で稽古ができました
今日も気温が高く蒸し暑い日ですが稽古場は空調を調節して快適な環境で稽古ができました
本日は軸を立てて中心で敵を捕らえることに注意して稽古していただきました。
軸がブレれば自ずと中心もブレたりズレたりします。
見えない敵を意識した居合稽古ですが自分なりに敵を意識し敵の中心を捉えることにも注意しましょう。
簡単ではありませんが、お互い頑張って稽古に励んでまいりましょう。
7月1日(火) 水道橋・剣術:関戸光賀
 今日はただ、同じ動きの繰り返し。
無駄が削れ、動きは静かに研ぎ澄まされてゆく。
今日はただ、同じ動きの繰り返し。
無駄が削れ、動きは静かに研ぎ澄まされてゆく。
6月29日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 稽古前にストレッチと膝行をする事で正中線の意識を高め半身から半身の転換と股関節を柔軟に使える感覚を感じてもらった後、五用、五応、五箇、走り懸り18本の各ポイントを確認しながら形の手順全体を繰り返し稽古しました。
稽古前にストレッチと膝行をする事で正中線の意識を高め半身から半身の転換と股関節を柔軟に使える感覚を感じてもらった後、五用、五応、五箇、走り懸り18本の各ポイントを確認しながら形の手順全体を繰り返し稽古しました。
7月4日は、アメリカがイギリスから1776年に独立を宣言した記念日となり、全米で今年は約7200万人が家族や友達と移動し花火大会やパレード、バーベキューで祝います。
セドナは山火事が懸念される為、花火の代わりにプロジェクションマッピングやレーザーでイベントを楽しみます。
6月29日(日)田町・居合:大隅幸一 師範
 暑さが堪える日が続いていますので熱中症に気を付けて稽古するようにしました。
暑さが堪える日が続いていますので熱中症に気を付けて稽古するようにしました。
本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
基本稽古で動きの確認を行ってから各自で動くようにしてもらいました。
いつも通り本日も雑にならないように丁寧な動きを意識しての稽古としました。
慣れてくると速さを求めるあまりに雑なものになってしまいがちです。
正しい動きや所作など基本を身に着けて、その先に進んでいけるように稽古していきましょう。先は無限大ですので頑張りましょう。
6月28日(土)秋葉原・剣術:五島博 師範
 朝から日差しが強く真夏のような天候の昌平シニア剣法稽古です。
朝から日差しが強く真夏のような天候の昌平シニア剣法稽古です。
何時ものように基本稽古の後、形稽古は刃引きの形四本目まで稽古を実施しました。
本日の形稽古は全員仕太刀だけでなく打太刀も稽古してもらいましたゆっくりした動きのなかでも正確な打ち込み位置や間合いを意識した動きで仕太刀の打ち込みをリードする難しさを体験してもらいました。
6月28日(土)赤羽・居合:宮澤和敬 師範代
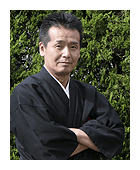 朝イチに開場した後、すぐに換気しながら冷房をかけたので、稽古が始まる時には快適な室温となりました。
朝イチに開場した後、すぐに換気しながら冷房をかけたので、稽古が始まる時には快適な室温となりました。
本日は軸をしっかり立てることを意識していただきました。
軸を立てたうえ、上下、左右のブレを無くすことで刃筋がしっかり通るように刀を振っていただきました。
また、柔らかな構え、抜刀について意識していただき、シンプルな動きが合理的に素早い動きに繋がるsことを確認していただぎました。
古武道の動きは、シンプルで力に頼らない柔らかな動きの中に合理的な理由があり、時代を跨ぎ継承されています。この動きを磨いていきましょう。
6月27日(金)西新宿・居合:小井健熙 指導員
 本日は初心者の方の参加でした。
本日は初心者の方の参加でした。
初心者、というのは貴重な期間だと思い知らされております。あの頃にこんな風に稽古すれば今こんなに苦しまなかったのに…などなど。そんな貴重な期間での稽古ですので、参加される方は焦らず、一回一回の稽古を大切に。指導担当はその方が歩む今後の武道を台無しにしないように丁寧に…と改めて感じました。
稽古では脱力せよ、と事あるごとに言いました。平日の稽古ですので、デスクワーク後の凝り固まった身体を解すように動く、とお伝えしております。その中で、呼吸は特に意識すべきかと思います。無呼吸だとどうしても身体は緊張してしまいます。動きと呼吸を合わせながら稽古を進めて参りました。
形は真を行いました。上段への構え直しを出している右脚ではなく左足股関節を緩めることで力を抜いて動くことができます。
順番としては真が最初の形になります。が、決して簡単などということはなく、むしろ大切なことを多く学ぼうとすれば困難な形だと思います。是非、他の稽古場で繰り返し行い、時たま教本などで学ぶべき事を確認しながらゆっくり稽古してみてください。
6月22日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 体軸のブレに注意し、敵対動作の意識をしてもらいながら、細かい点より先ずは形の手順を覚えてもらう為、繰り返し稽古回数の少ない五箇4本、走り懸り4本、特に神妙剣の重心移動と膝の緩め腹抜き動作を多めに動いて頂きました。
体軸のブレに注意し、敵対動作の意識をしてもらいながら、細かい点より先ずは形の手順を覚えてもらう為、繰り返し稽古回数の少ない五箇4本、走り懸り4本、特に神妙剣の重心移動と膝の緩め腹抜き動作を多めに動いて頂きました。
夏至を迎え稽古終了の午後7時過ぎは以前は外は真っ暗でしたのが、日の入りの午後8時過ぎまでは明るく夏の間は日の出も午前5時と一日が長く得した気分になれます。
6月22日(日)田町・居合:大隅幸一 師範
 本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
稽古に慣れてくると自分なりに楽な動きに陥り易いので注意するようにしたいです。
今日の稽古では最初の基本で動きと所作の確認をしながら丁寧に動いてもらいました。
また敵をイメージすることで動きにメリハリが出てくるのでそのことにも意識して稽古するようにしてもらいました。
いつになっても基本を大事にして稽古するようにしましょう。初心を忘れずに。
6月21日(土)横浜中山・居合:和田冠玄 指導員
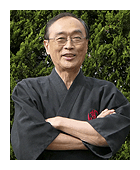 本日は横浜中山の初めての稽古でした。
本日は横浜中山の初めての稽古でした。
施設の広さは新横浜とほぼ同じで床は板張りです。照明、空調もしっかりしていて快適に稽古出来ました。
本日の参加者は全員傳位以上の方でした。其々ご自身の課題を意識しての稽古ができたかと思います。スペースの余裕も大きく真剣での稽古も安心感があります。
新横浜と横浜中山、二つの稽古場が横浜地区の稽古場として定着出来ればと思います。駅から近くですので東京からの参加も歓迎です。楽しく稽古が出来る場所にしていきたいものです。
6月21日(土)横浜中山・居合:中野瑞岳 指導補
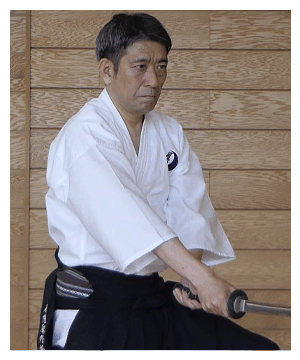 今日は梅雨の中休みの晴天でとても暑い日でした。稽古場も基本一、ニの頃には冷房がきいてきて気持ち良く稽古が出来ました。
今日は梅雨の中休みの晴天でとても暑い日でした。稽古場も基本一、ニの頃には冷房がきいてきて気持ち良く稽古が出来ました。
各々の状況で所作が必要になる場面があります。例えば刀礼から座技に続いて行った場合、正面向きの形であれば問題ないと思いますが、左月、右など左右に転身が必要な場合は身体の向きを座った状態で変えなければなりません。
転身後の頭、縦軸の位置は元の位置と同じ位置にする必要があります。その位置に落ち着かせる体と足捌きが必要になって来ます。
体と足捌きも慣れないと難しいので基本の稽古や形と同じで、地道に何度か繰り返して馴染ませて滑らかな動きで出来る様にしていきましょう。
私自身もそうですが無駄のない綺麗な所作が出来る様に一つ一つの動作に意識を向けて行きたいものです。
またご一緒に稽古を行いましょう。
6月15日と19日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *15日(日)体のバランスと体軸を整えるストレッチ後、五用、五応を丁寧に振ってもらいました。
*15日(日)体のバランスと体軸を整えるストレッチ後、五用、五応を丁寧に振ってもらいました。
特に形の初めと終わりの抜刀、納刀は細かい点まで指導しました。
*19日(木)仮想敵の位置に私が立ち、その間合いを感じながら、漢字の画数が一番多い「響返し」と「夢想返し」の書き順をホワイトボードで教え18の形のエアー習字後形稽古をしました。
ここセドナは本格的な夏に入り、朝晩は高原地帯で涼しいものの昼間は40度を超える日々となりますが、日本の様に湿気が無い事と9月迄モンスーン気候により晴天の日中でも短時間の急な強い雷雨に見舞われる事もありその後、日没時に東の空全体に大きな虹が現れるのも楽しみの一つでもあります。
6月21日(土)田町・居合:関戸光賀
 正しい素振りは、正しい構えから始まります。
正しい素振りは、正しい構えから始まります。
刀の軌道は常に直線的でなければなりません。なぜなら、それが最も敵に近く、最短で届く軌道だからです。
そのためには、自らの骨格をどのように変化させるべきか――その感覚を感じてください。
6月15日(日)秋葉原・居合:五島博 師範
 稽古場への往復もどうにか雨をさける事が出来ましたが湿度が高く汗ばむ天候でした、
稽古場への往復もどうにか雨をさける事が出来ましたが湿度が高く汗ばむ天候でした、
稽古始めに雑談で火曜夜の宗家稽古に傳位者以外も参加できる稽古に可能であれば参加する事の意義を(仏教や古流では師匠より面授を受けることが重要視され文字では伝わりづらい事を理解する事が出来るとされている?)話しました。
形稽古の左月、右では始めに無手による左右の転身を稽古しました、左月では左膝、右では右膝を一刀目の抜きはじめに開く事のないよう内転筋を締め敵の小手に付けると同時に左足(右足)を敵に向けて踏み出すよう稽古しました、又、その他の形稽古では個別に気付いた点を指摘して稽古を実施しました。
6月14日(土)品川・居合:山名宗孝 指導員
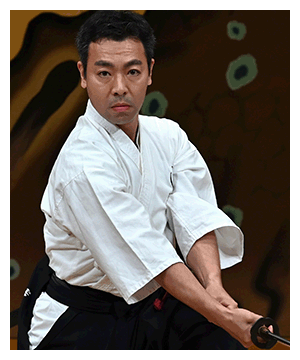 蒸し暑くなり、疲れが抜けにくい季節となりました。
蒸し暑くなり、疲れが抜けにくい季節となりました。
無理なく稽古を続けられるよう、体調を整えていきましょう。
稽古の取り組み方や、居合との向き合い方は人それぞれと思います。
私は不器用なのと気質柄、稽古中できない事をその場で何とか取り繕うと、つい頑張ろうとしてしまうのですが、稽古は頑張るものではないと考えていて、反省が多いです。
むしろ稽古に行けるよう体調や環境を整える事を頑張り、ゆっくり自身の居合を重ねて行きたいと思っています。
皆様はどの様に向き合われていますか。
6月14日(土)赤羽・居合:中野瑞岳 指導補
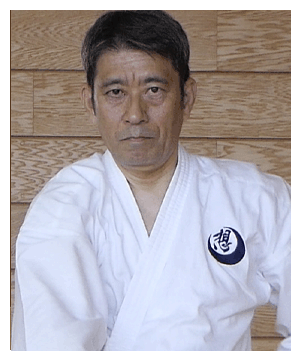 稽古内容を頭に記憶して次回に思い起こして活かす人、日頃から日記を付けて書き留めている人などそれぞれのやり方で次回へ繋げているのではないでしょうか。
稽古内容を頭に記憶して次回に思い起こして活かす人、日頃から日記を付けて書き留めている人などそれぞれのやり方で次回へ繋げているのではないでしょうか。
私は筆まめではないので携帯のメモ欄に気付いた点や指導頂いた点を帰りの車内で箇条書きで書き留めています。メモ書きは級の中頃から始めていて今では結構な量になりました。前回の内容を見て次の稽古ポイントに活用したりしています。
稽古をしていて上手くいかないなと感じられた時などは半年、一年前を見直したりすると出来た事を改めて確認出来て嬉しくなったり、出来ていない事に新たな気付きや反省したりとその都度湧き出た気持ちに小さな充実感を感じる事が出来ます。
自分なりに何か思い起こせる物を残す事で、迷った時の糧に繋げられられたらと思います。
6月13日(金)西新宿・居合:小井健熙 指導員
 稽古参加者から希望をお伺いしまして、基本の1、2と向抜、円要、玉光をゆっくりと稽古致しました。初心のうちだけとは言わず、ある程度形を覚えてもゆっくり動くことは肝要かと思います。動きの中で動作がしにくかったり、何処か痛むような箇所はないかな、と自分に問いかけながら稽古できます。一回だけではよく分からなくとも、何十、何百と繰り返し稽古しているうちに、無理がある部分は必ず動きを鈍くさせます。教本などで基本に立ち返りながら稽古を続けてみましょう。
稽古参加者から希望をお伺いしまして、基本の1、2と向抜、円要、玉光をゆっくりと稽古致しました。初心のうちだけとは言わず、ある程度形を覚えてもゆっくり動くことは肝要かと思います。動きの中で動作がしにくかったり、何処か痛むような箇所はないかな、と自分に問いかけながら稽古できます。一回だけではよく分からなくとも、何十、何百と繰り返し稽古しているうちに、無理がある部分は必ず動きを鈍くさせます。教本などで基本に立ち返りながら稽古を続けてみましょう。
残心や鞘の音なども気にされているようで誠に良い稽古ができました。以前にも書きましたが、少しずつ気を配れることを増やして上達できれば良いと思います。引き続き、ともに精進していきましょう。
6月8日と12日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *8日(日)ご夫婦の稽古日です。ご主人のH.Y.さんが6月10日〜7月31日までアラスカへお仕事で行かれますので、アラスカ滞在中空き時間があった時に手刀で立技と基本素振りの稽古が出来るようにその身体動作と注意点を伝え稽古しました。
*8日(日)ご夫婦の稽古日です。ご主人のH.Y.さんが6月10日〜7月31日までアラスカへお仕事で行かれますので、アラスカ滞在中空き時間があった時に手刀で立技と基本素振りの稽古が出来るようにその身体動作と注意点を伝え稽古しました。
奥様は引き続き稽古に来られます。
*12日(木)仮想敵の位置を考慮し、力まず、肩甲骨の開閉を意識した動きと半身の身体操作を注意してもらいながら、漢字の画数が多い陰中陽を新たに書き順を教え16の形のエアー習字後形稽古をしました。
昨夜は6月の満月「ストロベリー・ムーン」(アメリカ先住民が収穫時期を祝って名付けた「いちご月」)大きくピンク色した珍しい月で次に最も低い位置で満月が見れるのは20年後と聞き貴重なものが見れました。
6月8日(日)田町・剣法:関戸光賀
 棒の稽古では如何に合理的に体を使うかを学びます。
棒の稽古では如何に合理的に体を使うかを学びます。
一連の基本的な棒の特徴を捉えたら、その応用を考えてみます。
今日は皆なで形を一本作ってみました。
攻めと守りに矛盾がないか、無駄のない体捌きができているかを確認して動きを作ってゆきます。これをなん度も繰り返して練っていけば立派な一本の形になります。
学ぶということは時に実験も必要なことだと思います。
・・受けの違いについて考察する・・
6月7日(土)滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
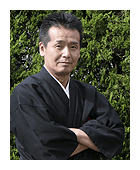 肌寒く感じる日もまだありますが、本日は朝から汗ばむような陽気で道場内にあるクーラーとサーキュレーターを動かしました。
肌寒く感じる日もまだありますが、本日は朝から汗ばむような陽気で道場内にあるクーラーとサーキュレーターを動かしました。
田町で同時刻に宗家稽古が行われていたことから、滝野川の参加者は級の会員さんが中心でした。
そのような事情から「軸の立て方、半身の使い方、足捌きや股関節の緩み」など基礎稽古の時間を長く取りました。
自分自身の稽古テーマでもある「上半身や腕に余計な力が入って力み過ぎている点」などの修正ポイントを伝えながら、会員さんそれぞれの気になった点を個別に指導して廻りました。
基本の一と二を稽古した後、形稽古は「真」「胸尽し」を行いました。
6月1日(日)池袋・剣術:関戸光賀
 いつもの基本稽古に続いて、本日は「無外流真傳剣法訣(十訣)」を行いました。
いつもの基本稽古に続いて、本日は「無外流真傳剣法訣(十訣)」を行いました。
これは無外流剣法の核をなすべき形ですが、残念ながら現在では失伝しています。この形の真髄を求め、かつて禅語と格闘しながら、言葉を形に昇華させていった日々を思い出します。
その探求の中で気づかされたのは、各形に宿る躍動感が、剣の道に生きる私たちに多くの示唆を与え、その崇高さを教えてくれるということでした。だからこそ、この形に臨むたびに思うのです。
これからも一つひとつの形と丁寧に向き合い、少しずつでもその意味を深めていけたらと--。
共に、精進して参りましょう。
5月29日と6月1日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *29日(木)棒を使っての半身の切り返しと膝を抜く動きを稽古。
*29日(木)棒を使っての半身の切り返しと膝を抜く動きを稽古。
胸尽しの漢字を新たに書き順を教え、全15の形の漢字のエアー習字後に形稽古をしました。
*1日(日)宗家の稽古日記の「一つひとつの形と丁寧に向き合う」と言う非常に意味深いお言葉を稽古時に伝へ形18本を丁寧に振りました。
6月1日(日)市川・居合:岩田和己 指導員
 前日の天候から一転、清々しい朝となりました。
前日の天候から一転、清々しい朝となりました。
本日は級から傳位まで幅広い方々が参加されました。
基本稽古では、刀を真ん中で取ること、鞘をしっかり引いての抜刀、真っ向斬りでは左腕を伸ばして前の敵を斬ること、剣体一致の動きなどいつもの注意点を確認しながら稽古しました。
形稽古は、本腰、玉光、陰中陽、夢想返し
本腰、陰中陽の足捌き、夢想返し二刀目の後ろの敵への体捌き、玉光では敵の斬りに対し重心を前に残したまま膝の緩みによる回避など、速く振って雑な動きにならないよう繰り返しゆっくりした動きで稽古しました。
ゆっくり動くことは意外に難しいですが、これによって軸がブレていないか、半身が切れているか、敵の正中線をとらえているかなど確認しながら正しい動きを身に着けていただきたいと思います。
5月31日(土)田町・居合:小井 健熙 指導員
 可動域、という言葉があります。各個人の柔軟性にも依りましょうが、足や腕はあらゆる方向に無限に動けるわけではありません。更に、力が入れやすいか、までを考えた際には、実は我々の身体は意外に自由がきかないな、と実感させられます。
可動域、という言葉があります。各個人の柔軟性にも依りましょうが、足や腕はあらゆる方向に無限に動けるわけではありません。更に、力が入れやすいか、までを考えた際には、実は我々の身体は意外に自由がきかないな、と実感させられます。
本日は正中線上で刀を扱うことについて学んでもらいました。基本の1などで顕著ですが、片手から両手に構え直す際、左手を必要以上に迎えに行くなどしておりませんか?刀を重く感じる一因かもしれません。
形でも、特に左手を迎えに行きやすい本腰、両車、陰中陽、野送りを行いました。自身の正中線上で刀を軽く扱えたでしょうか。私はあまり筋力がないので、できれば刀は軽く扱いたいところです。引き続き、一緒に稽古していきましょう。
流儀にもよりましょうが、腕を痛めたり怪我をしてからが一人前と考える方もおります。我々には関係ない話です。稽古をしていて、何かしらの痛みが続くようであれば、指導者や稽古仲間に相談する、病院に行く、稽古を休む、、、などして万全の状態で稽古にお越し下さい。その方が、稽古を楽しめると思いますよ。
5月22日と25日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *22日(木)股関節の脱力と膝抜きを意識した稽古。
*22日(木)股関節の脱力と膝抜きを意識した稽古。
画数の多い神妙剣と野送りの漢字を新たに書き順を教え、全14の形の漢字のエアー習字後形稽古しました。
*25日(日)日本に一時帰国されたS.Y.さんは、5月18日秋葉原の宗家の剣術と岩田指導員の居合を見学され、大勢での稽古場の迫力ある雰囲気とご自身が稽古されている居想無外流の居合を再認識され、素晴らしい見取り稽古出来たと稽古前に報告を受け、非常に感謝されておられました。
宗家、関戸師範初め当日の皆様がご親切にして下さり、この日記を通してお礼申し上げます。
S.Y.さん一層熱が入った稽古となり18日に見学された形を同様に指導しました。
アメリカは5月の最終月曜日がメモリアルデー(戦没者追悼記念日)で国の祝日となりますが、夏の始まりの日でもあり、学校も夏休みに入ります。
ここセドナも家族旅行者で街中、数多いハイキングトレイルも混雑してます。
5月24日(土)田町・シニア剣法:関戸光賀
 S剣の指導を行いました。
S剣の指導を行いました。
指導では、山名指導員、小井指導員、高橋指導補にお手伝いいただきました。ありがとうございました。
剣法は居合と異なり、相手がいるため、拍子や間合いの取り方を学ぶ良い機会となります。
また、剣体一致の重要性や、力みによる無駄があることも、相手を通して実感できるのではないでしょうか。
ここで得た学びは、居合の中でも多く活かされるはずです。
むしろ、同じ本質を異なる角度から見ることで、より実態が明確に浮かび上がってくると言えるでしょう。
S剣は、50歳以上の方を対象に、無理なくゆるやかに学べる剣術です。
5月24日(土)赤羽・居合:宮澤和敬 師範代
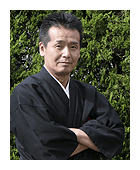 今朝は少し肌寒く感じる陽気でした。
今朝は少し肌寒く感じる陽気でした。
一般稽古3回目となる美大生のRさんが参加されました。
同じく稽古回数が4〜5回となる大学生のMさんも参加していたので、いつものように着付けと刀礼をベテラン会員さんが見守りながら、ご確認いただきました。
お二人ともご自身のペースで稽古を続けてもらいたいと思います。
本日の一般稽古は、攻めにおいても守りにおいても全てに大切で重要な「軸を立て正中線を外さない」という部分を意識していただきながら、参加人数が目の行き届く人数だった為、気になる点を個別に伝えていきました。
基本中基本であり、それ以上に奥が深い真っ向斬りの素振りを丁寧に繰り返し、リクエストのあった振り被り稽古、腹抜きと縦抜きの抜刀稽古を行いました。
基本の一と二を稽古した後、
形稽古は「左月」「円要」「野送り」を行いました。
5月18日(日)秋葉原・剣術:関戸光賀
 久しぶりに棒の稽古を行いました。
久しぶりに棒の稽古を行いました。
前回までは小太刀という短い得物での稽古でしたが、今日からは棒という、より長い得物を用いての稽古となります。
居想会での稽古においては、木刀であれ小太刀であれ、あるいは棒であっても、基本となる身体の使い方は変わりません。それぞれの武具の特性を身体が自然に理解していけば、どの道具を手にしても違和感なく扱えるようになっていくでしょう。
さらに、それぞれの得物の特性を掴むことで、他の道具における技にも冴えが生まれます。もちろん、居合における術理の運用もより一層深まっていくはずです。
とはいえ、やはり異なる得物を手にするのは、それだけで心が躍るものですね。その道具が自分の手の内に馴染み、日々自在に扱えるようになっていく過程は、何とも言えぬ喜びがあります。
5月18日(日)秋葉原・居合:岩田和己 指導員
 本日は2階多目的ホールにて剣法と居合の合同稽古が行われ、私は居合稽古を担当しました。
本日は2階多目的ホールにて剣法と居合の合同稽古が行われ、私は居合稽古を担当しました。
本日はまだ回数の少ない方から傳位の方まで、幅広く参加されました。
基本稽古では、しっかり鞘を引いての抜刀、身体全体を使って半身から半身への動き、股関節の緩みを使った動きを確認しながら動いていただきました。
これら基本の動きについても、まだ稽古回数の少ない会員さんにとってはスムーズな動きができず戸惑いを感じることもあると思います。
また、形稽古に至っては、座技、立技、前後左右転身ありで何が何やら・・・
久しぶりに、私が入会した当時の自分の動きを思い出しました。
周りの会員さんはいとも簡単に動いているのに、なかなか同じように動けず落ち込むことが多々ありました。
それでも、やめることなく続けてあと2か月で10年になります。
入会されてまだそれほど経っていない方、級が上がるにつれスランプに陥る方、稽古をしていくうち何度も悩みが出てくると思いますが、疑問に思っていること、悩んでいることありましたらどんどん指導部の方々に相談してみてください。きっと何らかの解決策が出ると思います。
そしてそれが居合を永く続けられる秘訣ではないかと思います。
5月18日(日)市川・居合:平澤昂円 師範
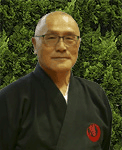 夜来の雨のせいか空気がしっとりし茉莉花の香りがいっそう引き立ちます。
夜来の雨のせいか空気がしっとりし茉莉花の香りがいっそう引き立ちます。
形稽古を拝見しているとどうしても刀を持つ右手の動きに注意が行くきらいがあります。今日は体の動きをメインに無刀の時の体がどう動くのか考えながら稽古をしてみました。
基本稽古の半身の切り替えの時、前の手の後ろに後ろの半身の手がきちんと添えられ身を守る動きになっているか、半身を前に引き出すとき手が先に動くのではなく後ろの半身が一緒に動くように、
形稽古は、右、野送り、響返し、右の敵です。基本稽古の延長で刀を持たず形をしたときの動きを確認していただきました。右。右の敵は抜刀を意識し、野送りは振り回すことなく左半身の動きに合わせること、響返しは半身を後ろに捌くことに刀が付いてくることを感じてもらいました。
右手だけでなく体全体が一体として動けば刀を振り回そうとする無駄な動きが少なくなるように稽古をしていけたらいいと考えています。
5月17日(土)品川・居合:山名宗孝 指導員
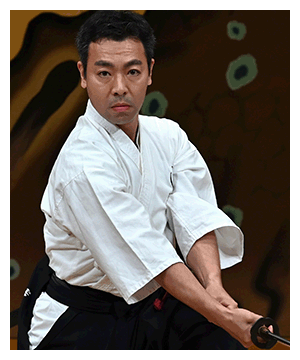 湿度も高く、床に足がペタペタとくっつくような感じでした。
湿度も高く、床に足がペタペタとくっつくような感じでした。
本日は先ずは剣体一致を心掛けて頂き、剣を体の延長線として扱えるのを目指し稽古しました。
またゆっくり丁寧に動作を行うだけでは、コマ送りの様になりがちで、体のどこを使い、どこで力が入り、どこで抜けているのか意識しにくいのかとも思います。
他人の演武を視て、良いと思ったところを何故良いと思ったのか、何か気がつくきっかけになるのではないでしょうか?
5月17日(土)秋葉原・居合:関戸光賀
 今日のように雨の日は、空気がまとわりつくようで、体も重く感じられます。
今日のように雨の日は、空気がまとわりつくようで、体も重く感じられます。
たぶん、湿度が高く気圧も低いのでしょう。
こんな日は無理にうまく動こうとせず、いつもよりゆっくり丁寧に、形を進めてみましょう。
自分の悪い癖を発見し、それを修正するための“ピント”をつかむには、むしろ絶好の稽古日和です。
5月8日と11日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *1日(木)基本の二の応用で逆袈裟に斬った後、切先で追い込み真向で斬る円要、前腰、右の敵を稽古。
*1日(木)基本の二の応用で逆袈裟に斬った後、切先で追い込み真向で斬る円要、前腰、右の敵を稽古。
後方の敵機を斬る縦の動きで向抜き、夢想返し。
各形は、仮想敵の間合いと目線に気をつけて貰いました。
本腰の漢字の書き順を教え、エアー習字後形稽古をしました。
*4日(日)毎週日曜はご夫妻の稽古ですが、奥様がこの日より日本一時帰国に付き、三回の稽古は一対一の指導となり、特に体幹を意識し姿勢と目線を重点に稽古をしました。
ここアリゾナ州はメキシコとの国境沿いでメキシコ文化の影響もあり本日Cinco(5日)de(の) Mayo(5月)シンコ・デ・マヨと言うお祭りです。
起源は1862年5月5日メキシコ軍がフランス軍に勝利した記念日でセドナの街もメキシコ音楽と料理でお祝いします。
5月11日(日)市川・居合:岩田和己 指導員
 本日の市川はほぼいつものメンバーでの稽古です。
本日の市川はほぼいつものメンバーでの稽古です。
基本稽古、形稽古ともに半身―正対―半身及びそれに伴う股関節の緩みと鞘引きをテーマとして稽古を進めました。
特に、基本稽古の素振り、抜刀では半身―正対―半身、鞘引きができても、基本の一、二を含む形稽古になると形の動きに捉われて基本的な動きの意識が飛んでしまいます。意識しないでもそのように動けるのが理想ですが、なかなか思うようにいきません。少しずつでも理想に近づけるよう、意識しながら動いてみてはいかがでしょうか。
今回は、基本稽古も形稽古もテーマを意識して、所作を分解しながらゆっくり動いていただきました。
次回は、また別のテーマを設けて稽古したいと思います。
そして、正しい動きを一つ一つ積み重ねていきましょう。
5月10日(土) 田町・居合:髙橋武風 指導補
 本日は基本の稽古を重点的に行いました。
本日は基本の稽古を重点的に行いました。
言葉で動作を伝える事の難しさを日々感じて居ます。
例えば左手で斬る、ですが左手が力んでしまい、剣尖が動いたり刃筋が曲がってしまったりと確かに左手で斬っているのに上手く行かない事があると思います。
なるべく分かりやすくお伝えしようと思って居ますが難しいところです。
分からない事、不明な点があったら遠慮なく聞いてくださいね。
5月10日(土) 赤羽・居合:宮澤和敬 師範代
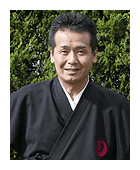 朝は冷たい雨が降っていましたが、室内は少し蒸し暑かったので冷房を入れました。
朝は冷たい雨が降っていましたが、室内は少し蒸し暑かったので冷房を入れました。
一般稽古2回目となる19歳大学生のMさんが参加しており、着付けと刀礼をベテラン会員さんにご確認いただきました。
Mさんは居想会ホームページへ掲載されている刀礼や居合形の動画を見ながら自己学習しているとの話で2回目とは思えないレベルで稽古へついてきていました。ご本人のヤル気をヒシヒシと感じて嬉しく思います。
他の参加者は動ける会員さんばかりだった為、下半身の足捌きと軸を中心に半身から半身の正しい動き方を重点的に意識していただきながら稽古しました。
基本稽古の流れから形稽古は「胸尽し」「玉光」「両車」を行いました。
5月10日(土) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
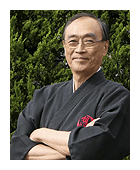 本日の参加者は全員傳位者で、其々ご自身の課題を持っての稽古でした。形稽古では手順一つ一つの正しい形を確認してもらっています。刀の取り方、敵を捉える足の動き、抜刀動作、切り終わりの形などなど、気になる癖になってしまっているようなところは其々の技量に応じて認識されているように思います。
本日の参加者は全員傳位者で、其々ご自身の課題を持っての稽古でした。形稽古では手順一つ一つの正しい形を確認してもらっています。刀の取り方、敵を捉える足の動き、抜刀動作、切り終わりの形などなど、気になる癖になってしまっているようなところは其々の技量に応じて認識されているように思います。
より精度を上げるよう、修正課題を意識して稽古することで技量の向上に繋げられると良いですね。
5月5日(月) 田町・居合:三浦無斎 師範代
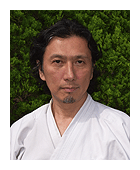 合宿、奉納演武も無事終了し、次の目標は秋の演武会となりました。しばらく間が空きますので、自分なりの目標を立てて稽古するのも良いと思います。
合宿、奉納演武も無事終了し、次の目標は秋の演武会となりました。しばらく間が空きますので、自分なりの目標を立てて稽古するのも良いと思います。
自戒も込めてですが、慣れてくると基本的な動きが疎かになっていても、気づきにくいんだな、と思いました。腹抜きの際に刀は横向いているか、向抜きの転身の際に
右足をちゃんと捌いているか、など。
出来ていると思っていることも、もう一度丁寧に確認していくことも、目標の一つに
なるのではないでしょうか。
秋までに精度を上げるべく共に精進して参りましょう。
5月1日と4日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *1日(木)基本の二の応用で逆袈裟に斬った後、切先で追い込み真向で斬る円要、前腰、右の敵を稽古。
*1日(木)基本の二の応用で逆袈裟に斬った後、切先で追い込み真向で斬る円要、前腰、右の敵を稽古。
後方の敵機を斬る縦の動きで向抜き、夢想返し。
各形は、仮想敵の間合いと目線に気をつけて貰いました。
本腰の漢字の書き順を教え、エアー習字後形稽古をしました。
*4日(日)毎週日曜はご夫妻の稽古ですが、奥様がこの日より日本一時帰国に付き、三回の稽古は一対一の指導となり、特に体幹を意識し姿勢と目線を重点に稽古をしました。
ここアリゾナ州はメキシコとの国境沿いでメキシコ文化の影響もあり本日Cinco(5日)de(の) Mayo(5月)シンコ・デ・マヨと言うお祭りです。
起源は1862年5月5日メキシコ軍がフランス軍に勝利した記念日でセドナの街もメキシコ音楽と料理でお祝いします。
5月4日(日) 池袋・剣術:関戸光賀
 居合と小太刀の稽古に共通するのは、何といっても刀を右手一本で扱うところです。
居合と小太刀の稽古に共通するのは、何といっても刀を右手一本で扱うところです。
だからこそ、小太刀の稽古では、空いている左手をどう使うかが大切になります。
自分の中心から力を出す意識が高まれば、居合の技もきっと上達するはずです。
合宿と奉納演武を終えて、次の剣法の課題に取り組みたいと思います。
短い得物である小太刀から、長い得物である棒へと稽古を進める中で、どのような技の変化が生まれるのか、楽しみです。
たとえ扱う得物が違っても、教えの根本は変わりません。
5月4日(日) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
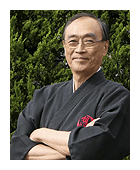 今日の稽古に入会して日の浅いℍが参加されました。新横浜稽古場の初参加は「初めまして」です。
今日の稽古に入会して日の浅いℍが参加されました。新横浜稽古場の初参加は「初めまして」です。
入会後、稽古回数が今日で9回目とのこと、まだ手順が分からないところも多く戸惑いがありながらも少しずつ慣れてきたように見えています。
稽古では柄の握り、刀の取り方、抜刀、納刀他の所作など基本動作を他の参加者にもそれぞれの技量レベル応じて、見直し稽古をして頂いています。すべてに通じることと思いますが、稽古を重ねて技量が上がってくると見えてくるものがまた変わってきます。
今日は、私自身も入会して始めたころのことをどうだったかなと思い起こさせて貰いながらの稽古でした。
5月4日(日) 池袋・居合:中野瑞岳 指導補
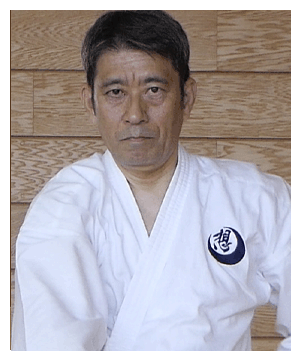 本日の池袋稽古は同時同場所で宗家剣法と居合が行われました。私の担当した居合稽古日記です。
本日の池袋稽古は同時同場所で宗家剣法と居合が行われました。私の担当した居合稽古日記です。
円要の初動は仮想敵が振り下ろした刀をかわす為、頭・上半身を右斜め前に捌きます。捌いた方向に頭・上半身が前傾して身体全体が振られてしまう感覚になる方がいると思います。
私もその様な時がありました長身や細身の人に感じられることかもしれません。元々体格や下半身がしっかりしていて体の重心が下半身にあったり体幹ができている人はその様なことはないのかもしれません。
頭、上半身は思ったより重いのでその動きに引っ張られない様にするには、身体を捻らない様に捌く方向に身体、足先を向けます。またいつもよりも意識して膝、股関節を緩めて縦の動きで身体を下げ重心をより低くなる様にします。
すると身体の振られる動きが抑えられて後ろへの転身がしやすくなる事がありますので一つの方法として試してみではいかがでしょうか。
稽古でよく聞くキーワードがあらゆる場面に出て来る事が分かります。
また、ご一緒に稽古を行って参りましょう。
5月3日(土) 田町・居合:五島博 師範
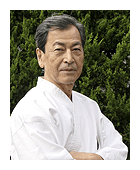 本日ゴールデンウィーク中日の稽古に8名の会員が参加してくれました、
本日ゴールデンウィーク中日の稽古に8名の会員が参加してくれました、
広々とした武道場に少人数の参加者でしたのでゆったりと稽古出来ました、
真っ向斬りの稽古に先立ち大きく敵に斬りつけるよう伝えました、敵の頭に物打ちが当たる時左の腕が伸びていることが大切です早く斬りつけたい為に肘が落ちてしまい小さな斬りつけにならない様注意が必要です、左肘が乳首の高さあたりで伸びて斬りつけるよう伝えました、又、形稽古では個別に気付いた点を指摘して稽古を実施しました。
以上田町稽古の報告です。
4月27日(日) アメリカセドナ稽古:松浦章雄 指導員
 ご夫妻の稽古日です。
ご夫妻の稽古日です。
身体バランス、呼吸を意識したストレッチ後、基本の一及び二それぞれ刀の支点に注意し、素早い振りかぶりを稽古。
形は真、身体を転身させる動きに注意しながらの向抜き及び夢想返し、ねじらない動きに注意しながら円要、本腰は右半身の崩しと同時に左半身が立ち上がる動きを繰り返しました。
野送りと玉光は仮想敵を特に意識し私が声かけした瞬間に抜刀してもらいました。
4月27日(日) 田町・居合:大隅幸一 師範
 本日は陽気も良くツツジやアメリカハナミズキが咲き誇っていて清々しい日でした。
本日は陽気も良くツツジやアメリカハナミズキが咲き誇っていて清々しい日でした。
本日は剣法と居合の同時稽古で、私が担当しました居合稽古についてです。
居合稽古は有傳者から新人までの幅広い層の方々でしたので、最初に動きや所作の説明を行ってから各自で動いていただきました。
また要所で更に修正していただく点を指摘して直すよう注意して稽古してもらいました。
個別には動きだけを真似て動かないで基本を大事にゆっくり丁寧に動くように注意していただきました。
特に初心者や新人の方に多く見られますので焦らず稽古して参りましょう。稽古を続けていけば必ず上達していけますので頑張りましょう。
4月26日(土) 秋葉原・居合:関戸光賀
 早いもので、御岩神社での奉納演武から一週間が経ちました。
早いもので、御岩神社での奉納演武から一週間が経ちました。
参加者の皆さんは、稽古を通じて確実に上達しました。
今年参加できなかった方も、ぜひ次の機会にチャレンジしてください。
清らかな空気と厳かな場での演武は、成長に欠かせない大切なエッセンスだと感じます。
さて、来週は武徳祭での演武が控えています。
京都・武徳殿で行われるこの武徳祭に招待されたことは、居想会にとって大変光栄なことです。
4月26日(土) 市川・居合:平澤昂円 師範
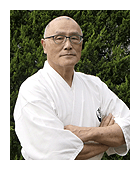 合宿稽古に続いての御岩神社での奉納演武いかがでしたでしょうか、深山幽谷を思わせる杉木立に囲まれた荘厳な雰囲気の中での演武は何物にも代えがたい経験をさせていただきました。神主さんの詔に頭を下げていた時本殿の下の方から爽やかな風が吹き出してきた不思議な体験をしました。
合宿稽古に続いての御岩神社での奉納演武いかがでしたでしょうか、深山幽谷を思わせる杉木立に囲まれた荘厳な雰囲気の中での演武は何物にも代えがたい経験をさせていただきました。神主さんの詔に頭を下げていた時本殿の下の方から爽やかな風が吹き出してきた不思議な体験をしました。
今日の稽古は半身の切り替えを意識しての稽古になります、左右の軸ではなく体の中心の軸を中心に縦の動きをするにはどのように体の緩みを使うか、考えながらの稽古です。腕力ではなく半身の切り替えを使った素振りが出来たらいいですね。
秋の演武会に向けてまた日々の稽古の積み重ねです、目的をもって稽古をすることは大切なことだと考えます。
4月20日と24日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *20日(日)ご夫妻の稽古日です。
*20日(日)ご夫妻の稽古日です。
昨年11月中旬に注文した居合道具一式が、日本から5ヶ月を要し無事税関も通過入手しました。ご自分達に合った新しい道着と居合刀で一層稽古にも熱が入り、股関節を意識したストレッチ後、基本稽古を実施。
新たに右の敵、響返しを指導し計18本の形の動きと特に新し刀での抜刀、納刀にも注意を払って貰いました。
*24日(木)居合に於ける身体の使い方も大分慣れてこられましたので、基本稽古を正しく確実に速さも加え剣体一致を意識し、形は五箇・走り懸りを中心に、合わせ居合を五用・五応から3本づつ選び稽古をしました。
本日も形稽古をする前にその都度形の漢字を発音しながらエアー習字をしてから行いました。
御岩神社の神聖な場所での奉納演武と歴史ある合宿先の道場での気合の入った素晴らしい写真をHome pageより拝見させてもらいました。
4月13日と17日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *13日(日)ご夫妻の稽古、先週に続き膝行も加え基本の後、新たに陽中陰を指導、特に抜刀時の捌きと体軸を意識し、16の形を始める時の呼吸にも意識して稽古しました。
*13日(日)ご夫妻の稽古、先週に続き膝行も加え基本の後、新たに陽中陰を指導、特に抜刀時の捌きと体軸を意識し、16の形を始める時の呼吸にも意識して稽古しました。
*17日(木)ストレッチ時には股関節、膝の緩みを意識しながら半身の入れ替えやスクワットをし、基本稽古で真っ向斬りを特に沢山振ってもらい、今迄稽古した16の形に加え新たに「響返し」及び「右の敵」で膝の緩みと転身する動きを稽古しました。
これまでに漢字で7つの形を書ける様に教えて来ましたが、本日は形稽古をする前にその都度漢字を発音しながらエアー習字をしてから行いました。
我が家の庭には現在紫色の花菖蒲が満開で日本と比べ1ヶ月ほど早くこれからセドナは夏に向かい暑くなります。
いよいよ御岩神社の奉納演武と合宿ですが、どうぞ深呼吸で心穏やかに、特別な緊張感も同時にお楽しみ下さい。
4月15日(火) 水道橋・居合:関戸光賀
 御岩神社での奉納演武も近づいてきました。
御岩神社での奉納演武も近づいてきました。
日々の稽古は自分自身と向き合うものですが、演武はギャラリーの目がある分、独特の緊張感が伴います。
実力の9割程度の力で臨むくらいが、ちょうど良いでしょう。
平常心を保ち、落ち着いて挑みましょう。
本日、イギリスからの見学者が入会を希望されました。
また、日曜日にも見学に来られた方が入会されました。
いずれも20代の外国人の方で、日本文化に興味を持ち、学ぼうとする姿勢は嬉しいことです。
4月12日(土) 品川・居合:五島博 師範
 暖かい過ごしやすい天候の朝でした、
暖かい過ごしやすい天候の朝でした、
初めに同日、田町で実施されている奉納演武の稽古やこの秋に開催予定の演武会に向けての人に見てもらうことを意識した稽古をすることで技量がよりアップすることが可能であることを伝えただ形の所作をただなぞる稽古にならない様に心掛けるよう伝え稽古をしました、
又、特に初心者の方々には教本の利用は事前に教本を読んで覚えるより本日稽古した形の内容を家にかえつて教本で復習することの方が理解しやすいことを勧めました。
4月6日と10日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *6日(日)
*6日(日)
ご夫妻の稽古、ストレッチに膝行も加え基本の後、形は五用・五応それに水月、前腰、夢想返しを稽古。
新たに陰中陽の足捌きと神妙剣の足運びと重心移動しつつの腹抜き転身時の緩みの稽古を多めにしました。
ご夫妻の居合道具一式は日本から発送準備が出来た旨連絡を受け、アメリカ到着後相互関税の通関次第ではありますが航空便で10日間位で入手出来るのではと本格的にご自分の居合刀での稽古を楽しみにされてます。
*10日(木)
基本稽古で正しく真っ向や袈裟を斬っているかの確認で柄頭の運びと刃筋と間合いを意識し振ってもらいました。
今迄稽古した15の形に加え神妙剣を新たに指導しました。
今迄に漢字で7つの形が書ける様に指導し、それをご自宅で書き込んだ練習帳を見せてもらいましたが、正しく書かれており努力に感心させられました。
セドナ4月初旬は雪が降って結構寒かったのですが、現在は昼間30度ぐらいまで上がり空気が乾燥している為、暑さは然程感じませんが春を通り越し初夏がやって来た感があります。
赤岩に囲まれ新緑と青空、草木の花々と心を明るく軽やかにさせられる季節です。
東京も最後の桜をお楽しみ下さい。
4月6日(日) 池袋・剣術:関戸光賀
 初心の方々も、近頃は動きに練れが見られるようになり、嬉しき限り。
初心の方々も、近頃は動きに練れが見られるようになり、嬉しき限り。
今は、急がず焦らず、正しき所作を一つひとつ身につけて参りましょう。
本番の折には、皆が堂々たる姿をお見せできることと、楽しみにしております。
4月6日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
 気温の乱高下もこれでやっと落ち着きを戻したのでしょうか?
気温の乱高下もこれでやっと落ち着きを戻したのでしょうか?
今朝は曇って多少気温は低かったようですが稽古にはうってつけの気候でした。
本日は、いつものメンバーに加え久しぶりにYさんが参加されました。4月に入って仕事のほうもやっと落ち着かれたそうで、これからはできるだけ稽古に参加して、居想会の動きに慣れていただきたいと思います。
今日の稽古では基本稽古も、形稽古も、軸のブレ、刃筋、手の内の緩みに加え、半身(鞘引きによる半身、振りかぶり時の半身)を意識し、腕に頼らず体全体を使った抜刀、斬りに重点を置きました。
本日の稽古形、眞、胸尽くし、水月、前腰は、皆さん何度も稽古されている形なので半身を意識して動くことも問題なくこなせたのではないかと思います。
これからも一つ一つテーマを設けて正しい動きを身に着けていきましょう。
4月5日(土) 品川・居合:山名宗孝 指導員
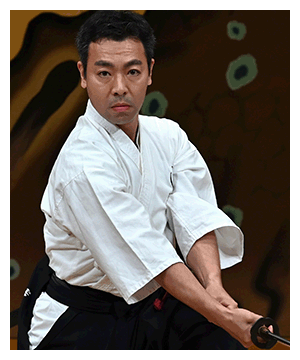 本日は斬る場所に届く斬りつけができるよう抜刀と、転身の際の身体の使い方を意識した稽古としました。
本日は斬る場所に届く斬りつけができるよう抜刀と、転身の際の身体の使い方を意識した稽古としました。
抜刀は刀の取り方から斬り終わりに至るまで、どのような動きをしているのか、書こうとすると、とんでもなく長くなります。
時には自分の体のどこの力をどう使って抜刀しているのか、分析してみると良いかもしれません。
斬り終わりだけに意識を取られるのではなく、斬るための抜刀をしたいですね。
4月5日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
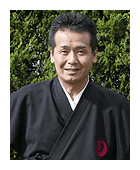 爽やかな青空で心地良い朝でした。稽古が始まると少し汗ばむくらいだった為、大型扇風機を廻しました。
爽やかな青空で心地良い朝でした。稽古が始まると少し汗ばむくらいだった為、大型扇風機を廻しました。
本日から19歳の大学生Mさんが初稽古です。同じ若手として初心者講習を小井指導員が担当してくれました。
剣道をやっていたとの話で着付けも1人で大丈夫でしたが、居合と剣道の着付けの違い(帯刀する)を中野指導補がフォローしてくれました。
稽古後にご本人も楽しかったと言っていたので、是非とも続けてもらいたいです。
他の参加者は稽古手順が頭に入っている会員さんばかりだったので、身体の中心線である正中線をいつも以上にシビアに意識していただき、半身の正しい使い方と身体のバランスを重点的にチェックしながら稽古しました。
若い方が居合や剣術に興味を抱いて居想会の仲間となることは大変嬉しいことです。
4月4日(金) 西新宿・居合:小井健熙 指導員
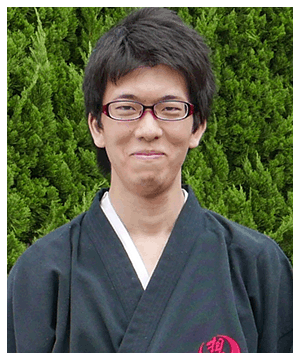 新稽古場所の初日は予想より多くの人にお集まり頂きました。
新稽古場所の初日は予想より多くの人にお集まり頂きました。
少々遅い時間で、それも仕事帰りでお疲れだったでしょうが、皆さんしっかり動いておりましたね。
稽古でも話しましたが、一回の稽古で得られることはあまり多くありません。しかし、それを積み重ねることで技量が上がっていきます。是非、稽古にどんどん参加して一緒に精進して参りましょう。
本日は基本動作に時間を割きました。それでも、気にすることは山ほどあります。足の向きから腕の伸展、呼吸に目附けまで。各自の技量に応じて指摘をさせて頂いたつもりです。次回の稽古ではそれが成っており、また別のことに気を配れるようになっていれば誠に良いと思います。
場所柄、音を立てることを控えてました。が、そもそも足音や鞘鳴りは稽古には無用です。静かに動き、滑らかに抜刀すれば身体も刀も痛むことなく長く稽古を楽しめます。引き続き、丁寧に動くように心がけましょう。
3月30日(日) 秋葉原・居合:大隅幸一 師範
 昨日とは違い良い天気になりました。
昨日とは違い良い天気になりました。
稽古の休憩時には窓から満開の桜で花見ができました。
本日は、広々としたスペースを活用して走り懸り4本を稽古しました。
走り懸りは、走りの動きを止めずにその動きを一刀目に繋げていきます。
そのためには、軸をブラさずに緩みを使う必要がありますが、それがなかなか難しいです。
稽古を積むしかないですね。
お互いに頑張て精進してまいりましょう。
3月29日(土) 滝野川・居合:三浦無斎師範代
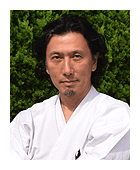 稽古の際に、指摘を受けて簡単に修正できることもあれば、
稽古の際に、指摘を受けて簡単に修正できることもあれば、
わかっちゃいるけど修正できないんだよな、ということもあると思います。
とはいえ、基本的な体の動きが身につかないと本当には修正できていなかったり・・・時間かかるな、と思っていたことが一つのヒントで意外とすんなり修正できたり・・・
修正できたと思ったことが、次はうまくできなかったり・・・
そんな行きつ戻りつは悩ましいものですが、そんな状態も楽しんで稽古できればなぁと思います。
奉納演武も近づいてきました。
焦らずそして貪欲に、楽しんで頑張って稽古を続けましょう。
3月29日(土)シニア剣法:五島博 師範
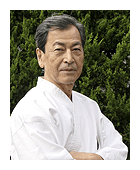 冷たい雨がふり冬に戻ったような天候で大崎駅から稽古場所に向う目黒川を渡る御成橋からみる桜並木も六部咲き程度にとどまっているようです、
冷たい雨がふり冬に戻ったような天候で大崎駅から稽古場所に向う目黒川を渡る御成橋からみる桜並木も六部咲き程度にとどまっているようです、
何時ものように基本稽古の後、刃引きの形の一本目と二本目、及び乾坤の形の二本目野送りと三本目の玉光を稽古しました。
立ち合う相手との間合いを近からず遠からず適度な間合いを保ちつつ打ち込みそして受けるあるいは受け流す、単純なようでなかなか難しい事です繰り返し注意して稽古を続けたいと思います。
3月29日(土) 田町・居合:岩田和己 指導員
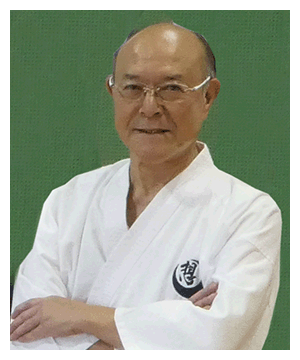 昨日までの夏日から一転、雨も降って10℃を下回る寒さとなりました。
昨日までの夏日から一転、雨も降って10℃を下回る寒さとなりました。
本日の一般居合は宗家剣法と同フロアーでの稽古でした。
居合の参加者は比較的少なかったのでゆったりと稽古することができました。
今回の基本稽古では膝、股関節の緩みとともに半身を意識して身体全体で斬るよう心掛けていただきました。
毎回、稽古はこれらの基本稽古から始まります。会員さんの中には、毎回同じ稽古でウンザリと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった基本動作がしっかり身についていないと、形稽古を行っても正しい動きができません。なぜなら、すべての形は基本稽古のエッセンスが詰まっていますから。
少しずつでも構わないと思います。覚えたことは常に活かせるようにしましょう。その積み重ねが形に反映されてくると思います。気長に楽しく稽古をしていきましょう!
3月23日(日) 田町・居合:関戸光賀
 本日は、日立武道館での合宿に関する説明と、御岩神社での奉納演武のシミュレーションを行いました。
本日は、日立武道館での合宿に関する説明と、御岩神社での奉納演武のシミュレーションを行いました。
その後、それぞれの演武の組みに分かれ、御岩神社での演武の形を合わせました。
演武時間は短いですが、気迫を込めて居合や剣術の形を行えば、ギャラリーの方々にもその想いは伝わるはずです。
また、当日は回向祭でもあり、多くの方々にご覧いただける機会となります。
自分自身とチームのレベルをどこまで高められるか。
日々の稽古を疎かにせず、しっかりと準備を進めましょう。
3月22日(土) 赤羽・居合:中野瑞岳 指導補
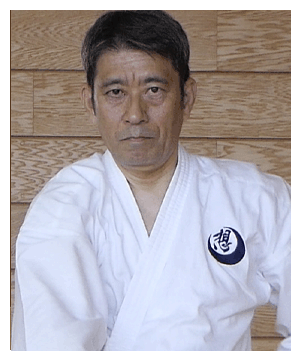 朝は空気が冷たかったのですが、稽古後の駅前では小春日和の暖かさをとても感じられました。
朝は空気が冷たかったのですが、稽古後の駅前では小春日和の暖かさをとても感じられました。
形の立技は柄を真ん中で取る所から始まり血振りをして納刀で終わります。
最後まで意識をして行いたいですが形や抜刀で集中した意識が最後に途切れてしまい、その後は何となくという動作になってしまう時が稽古に慣れてくるとある様です。
私も以前にその様な時がありました、その時指導担当の方から「勿体無い」と注意を頂きました。せっかく自身で作った佇まいが途切れてしまいますから本当そうです。
起承転結とも言われますが初動から終わりの両手を降ろして遠山まで技の出来不出来だけではありません。自身で仮想敵を捉えて作り出す間合いですので最後まで意識を集中して行けたら良いですね、全体に居合を感じられる時を創れたら更に良いですしその世界観は大切にしたいものです。
また、ご一緒に稽古を行って参りましょう。
3月22日(土) 市川・居合:平澤昂円 師範
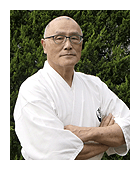 数日前の雪が嘘のようにさわやかな陽光です。暑さ寒さも彼岸まで、庭の桜桃もいつもの年より多く花が付いたようです秋のサクランボが楽しみです。
数日前の雪が嘘のようにさわやかな陽光です。暑さ寒さも彼岸まで、庭の桜桃もいつもの年より多く花が付いたようです秋のサクランボが楽しみです。
来月の御岩神社奉納演武を踏まえ18本の形の注意点を確認しながら稽古をしてみました、稽古の前に教本を確認してみると入会した当時に書き込んだ注意点が散見されます。その当時どのように形を稽古していたか懐かしく思い出されます。緩みとゆう言葉が多く書き込んでありますが果たしてどうとらえていたか、今も悩んでいます。
奉納演武が終わればすぐに秋の演武会と会は動いていきます。少しでも技量を上げるように稽古をしていきましょう
3月20日(金) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
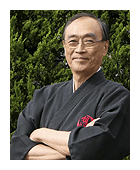 本日はいつもより少し多くの参加で真剣での稽古参加もありましたが、皆さん在籍も長く多く稽古回数重ねている方で、各自周囲に配慮しながら安心安全に稽古出来たかと思います。
本日はいつもより少し多くの参加で真剣での稽古参加もありましたが、皆さん在籍も長く多く稽古回数重ねている方で、各自周囲に配慮しながら安心安全に稽古出来たかと思います。
稽古では其々癖になっていそうなところやブレ等、細かなところに精度を求めて個別に指導させて頂きました。
御岩神社奉納の稽古も始まっています。各々御自身の目標とその課題を意識して稽古することで少しずつでも技量の精度を上げていきたいですね。
3月16日と18日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *16日(日)ご夫妻の初心者稽古、基本の後、形は五用・五応を稽古、仮想敵を意識しながら間合いと斬る刃筋を確認して数多く振ってもらいました。
*16日(日)ご夫妻の初心者稽古、基本の後、形は五用・五応を稽古、仮想敵を意識しながら間合いと斬る刃筋を確認して数多く振ってもらいました。
*18日(火)ご夫妻は毎週日曜に来られるのですが、来週の日曜は都合が悪くその代替で、お仕事終了後の稽古となりました。
道場は北側の壁一面がスライド鏡で日頃は自分の姿を映してましたが、今回はスライド鏡を背にして南側のスライドガラスに向き庭の木々を見ながら稽古をしました。
基本稽古後は五用・五応と新たに、走り懸りの体勢と進みの稽古を重ね、前腰と水月を指導しました。
3月16日(日) 池袋・剣術:関戸光賀
 御岩神社での奉納演武に向けた剣術の稽古が始まりました。 演武の組み合わせも決まり、本日はその初稽古となります。 この一ヶ月を有意義に過ごし、良い成果を目指していきましょう。
御岩神社での奉納演武に向けた剣術の稽古が始まりました。 演武の組み合わせも決まり、本日はその初稽古となります。 この一ヶ月を有意義に過ごし、良い成果を目指していきましょう。
3月16日(日) 品川・居合:大隅幸一 師範
 寒く雨の中みなさん熱心に稽古に参加しておりました。
寒く雨の中みなさん熱心に稽古に参加しておりました。
日々の寒暖差が激しく体調に気を付けたいですね。
本日は足の動きで特に爪先を敵に向け捉えて動くことをポイントとしました。
最初の半身の切り替えしの基本稽古で常に前足の爪先が敵に向けて出されているかをしっかり確認してもらい、その後の基本や形稽古においても注意していただきました。
軸を保つことは勿論ですが、爪先とともに自分の中心で敵を捕らえることも大事です。
上体は意識していても足元が疎かになりがちなので注意しましょう。
3月15日(土) 品川・居合:髙橋武風 指導補
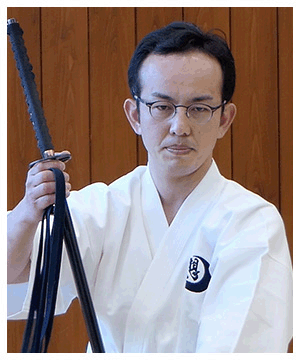 本日は自分の位置と敵の位置を特に意識して稽古しました。
本日は自分の位置と敵の位置を特に意識して稽古しました。
敵との距離感を理解して稽古すると形の完成度が変わって来るかと思います。
さらに自身の置かれている状況を想定すると形の意味が理解しやすくと思います。
意識するだけなので他に必要な物はありません。
意識する、試してみては如何でしょうか。
3月15日(土) 池袋・居合:関戸光賀
 今日の稽古場所には鏡があり、自分の動きを確認しながら稽古していただきました。
今日の稽古場所には鏡があり、自分の動きを確認しながら稽古していただきました。
指摘されるよりも、自分で気づいて修正していく方が上達につながると思います。
しかし、誤った思い込みを持ったままだったり、鏡に映る自分の姿を正しいと錯覚してしまったりすると、この環境を十分に活かすことができません。
指導者は、時には正しい方向へ導き、美しい動きを伝えてください。
3月15日(土) シニア剣法:五島博 師範
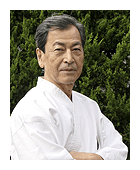 昨日の暖かい日から少し寒さの戻った午前のシニア剣法稽古です
昨日の暖かい日から少し寒さの戻った午前のシニア剣法稽古です
前回の稽古報告でも伝えましたが立ち合う相手のどこに斬りつけているのか敵の打ち込みに対し自身の身を守り正しく受けているか敵の中心を取っているかなど難しい事がいっぱいです。
見方を変えれば実態のない仮想敵を相手の居合を演武する難しさを再確認しました、
以上シニア剣法稽古の報告です。
3月9日と13日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
*9日(日)ご夫妻の初心者稽古、基本を丁寧に前回の形に加え新たに、体の軸がブレない稽古として「本腰」、膝の緩みと前重心を残す左半身での抜刀の稽古として「玉光」を指導しました。
これで五用、五応10本の全体動作、流れを感じ取ってもらいました。
*13日(木)形15本を稽古、「陽中陰」の抜刀時の捌きと振りかぶり、「胸尽し」の抜刀事と体軸を特に注意しながら繰り返し行いました。
前回に続き、休憩時間を利用し、形の名前「両車」を漢字で書き順を教えました。
来週木曜日は娘さんの学校が春休となり、稽古に来れない為、宿題として計7つの形を漢字で書ける様に自宅で練習した用紙を再来週、私が添削する予定です。
3月9日(日) 品川・居合:山名宗孝 指導員
 私事ですが、体調を崩しお休みしておりました。付き合いの長い自分の身体ですが、体調の管理もままなりませんね。
私事ですが、体調を崩しお休みしておりました。付き合いの長い自分の身体ですが、体調の管理もままなりませんね。
思うように身体や刀を扱うこと、ままなりませんね。
居合も同じ動作を繰り返し稽古し、身体に動作を覚え込ませます。稽古を重ね、応用を利かせた動作が、咄嗟にできるようになりたいものです。
ところで、剣体一致ができるようになったら、身体の動きに漫然と委ねるのでなく、仮想敵を意識すると居合が変わってきます。より隙が少なく緊張感が感じられますね。
3月9日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
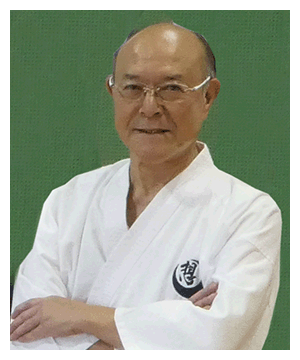 昨日は夕方にはみぞれから雪に変わり、翌日の稽古が中止になるのではと心配になりましたが、朝から好天に恵まれ絶好の稽古日和となりました。
昨日は夕方にはみぞれから雪に変わり、翌日の稽古が中止になるのではと心配になりましたが、朝から好天に恵まれ絶好の稽古日和となりました。
本日の参加者は、ほぼいつものメンバーと久々に市川に来られた方。
基本稽古も形稽古も、膝、股関節、手の内の緩みを意識し、まずはゆっくりした動きの中で、軸のブレ、刃筋に注意しながら稽古をすすめました。
基本の一、二では、各自前方の一か所を仮想敵とし、それに向かって真っすぐ斬り進めば左右のブレを防ぐことができると思います。
形稽古は、本腰、玉光、前腰、夢想返し、神妙剣、右の敵の6形。
各形それぞれ膝の緩み、股関節の緩み、手の内の緩みにより正確な動きができると思います。まずはゆっくり動いてどのように緩めばよいのか試してみてください。回数を重ねるうちに正しい動きが身に着くと思います。
3月8日(土) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
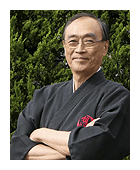 本日の稽古参加者は全員傳位以上の方でしたので、技量はそれぞれ一定のレベルには達しています。稽古では細かいところを一つ一つ確認して精度を上げることを意識してもらっています。帯刀の状態、柄の取るところから始まって、抜刀から納刀までいろいろな動作をチェックすると長い間の稽古の中で自己流の癖がついていることに気付くこともあるかと思います。そこを意識して修正できるようになれば良いですね。
本日の稽古参加者は全員傳位以上の方でしたので、技量はそれぞれ一定のレベルには達しています。稽古では細かいところを一つ一つ確認して精度を上げることを意識してもらっています。帯刀の状態、柄の取るところから始まって、抜刀から納刀までいろいろな動作をチェックすると長い間の稽古の中で自己流の癖がついていることに気付くこともあるかと思います。そこを意識して修正できるようになれば良いですね。
分かりきっていることと思いがちなところも、時々は意識してチェックしてみることも大事かなと思います。
3月8日(土) 赤羽・居合:中野瑞岳 指導補
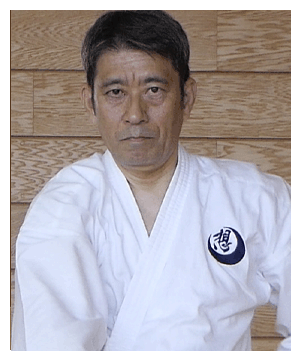 今朝の寒さに合わせて稽古場のクーラーを会員さんの協力を得て最初暖房、そして冷房にして最終送風で落ち着き体を動かしやすい環境で稽古出来ました。
今朝の寒さに合わせて稽古場のクーラーを会員さんの協力を得て最初暖房、そして冷房にして最終送風で落ち着き体を動かしやすい環境で稽古出来ました。
手の内の緩みは常に大切です。例えば夢想返しの一刀目から2刀目への転身時の柄の握りなどは分かりやすい一例ではないでしょうか。
正中線を意識した最短の動きを産む為には切先を下げない様に気をつけ左右の手の内の緩みを充分行って左手で柄や刀を導く手捌きも必要です。そして転身先の相手を斬る瞬間に柄を握り込んで行きます。
この様に理にかなった無駄のない動きから緩急が生まれて早さにも繋がって行きます、その様な動きが出来たとき見るものが美しく感じられると思います。私もそこを目指して精進して参りたいです。
またご一緒に稽古を行って参りましょう。
3月8日(土) 田町・居合:小井健熙 指導員
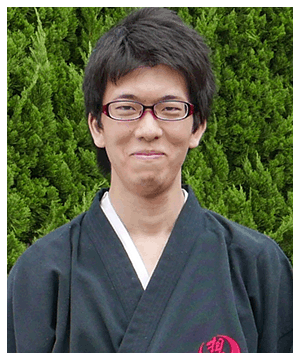 毎回の稽古で行なっている半身の入れ替えですが、稽古の終わりまで意識できているでしょうか。稽古中盤にはつい忘れて腕の力で刀を振っていた…なんてことは誰もが通る道です。未だに自身も気をつけていることでもあります。
毎回の稽古で行なっている半身の入れ替えですが、稽古の終わりまで意識できているでしょうか。稽古中盤にはつい忘れて腕の力で刀を振っていた…なんてことは誰もが通る道です。未だに自身も気をつけていることでもあります。
本日の稽古では半身を意識して頂きました。特に座り技を多く実施した本日でしたが、最後まで半身…とりわけ左半身の意識を保てたでしょうか。利き手、と同じように利き足があり、足から繋がる身体にも左右で強弱の差があります。本日行なった形の中に陽中陰がありますが、左半身を大きく運用しないと抜刀することがかないません。まさしく「手抜き」とならないように形を為せているか。この形に限った話ではありませんが注意しながら稽古を重ねてみて下さい。
稽古は自分の悪癖を壊す行いですが、良い部分を精錬していくことでもあります。慎重に稽古を積み重ね、良い部分まで壊してしまわぬように気を付けてみて下さい。
座した体勢からの動きが多くて大変だったと思いますが、辛そうな顔をしている方はいなかったように見受けます。少しずつ座りの体勢に慣れてきている証拠です。無理は禁物ですが、引き続き一緒に頑張っていきましょう。お疲れ様でした。
3月8日(土) 田町・居合:関戸光賀
 シニアの剣法、通称「S剣」が昨年度より開始され、多くの参加者で賑わっています。
シニアの剣法、通称「S剣」が昨年度より開始され、多くの参加者で賑わっています。
居想会で行う剣法は、基本的な体の使い方が居合と共通しているため、剣法の稽古が進むにつれて、自然と居合での動きにも変化が現れます。
即物敵な例として、今日行った「両車」の三刀目は、廻剣を応用することで、より素早い斬りへとつなげることができます。
3月2日と6日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
*2日(日)ご夫妻の初心者稽古、基本と前回の形に加え新たに「右」と「野送り」計7つの形を居合刀の配送を待つ間、鞘付きの木刀を使い、形の理合を含め指導。
*6日(木)新たに指導する形「陽中陰」は右・左足の捌きと抜刀、腰の浮かしと振りかぶりと体軸を学ぶ一本の形に奥深さを感じて貰いました。合計十五の形を稽古しました。
漢字で形の名前「円要」の書き順を教えました。
#先週ご報告しました『アリゾナ祭り』の続編です。
会場はフェニックス市の中心にある大きな公園全体を利用し日本的な屋台、雑貨等の出店で日本文化が紹介されました。
野外ステージは4箇所あり、その一つが武道ステージで、居合グループの流派は新心流、荒木流、真剣道の演武を見ました。
レベル的には力任せで剣体一致の動きや、礼に始まり礼に終わる所作が出来て無いのが残念に思いました。
居想無外流居合を稽古している私にとっては、来年2月に現在の生徒3名と一緒に本来の居合における所作や体捌きをこのステージで演武出来れば、居合に対するイメージが変わるのではと思った次第です。武道出場者に日本人はいませんでした。
因みに屋台で売っているものは、やきそば$15(2,250円)、お好み焼き$12(1,800円)、小さい鯛焼き2個$10(1,500円)、ラーメン$18(2,700円)など大人気でした。価格は高いです。
3月2日(日) 秋葉原・居合:五島博 師範
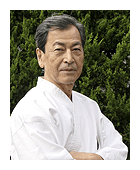 暖かい午後の稽古時間でしたのでエアコンはオフにして換気のみの設定でも快適に稽古をする事ができました、
暖かい午後の稽古時間でしたのでエアコンはオフにして換気のみの設定でも快適に稽古をする事ができました、
本日はゆるみによる重心の移動による動きのきっかけに注力して稽古してもらいました。
特に立技において動き出す方向にある脚の緩みにより重心を移動させ後ろ脚の蹴りに頼る動きにならない様に動き出すことを意識し稽古してもらいました。
以上品川稽古の報告です。
3月1日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
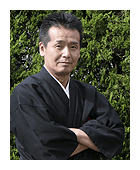 爽やかな気候で稽古日和な朝でした。女性会員さんの参加が多く、賑やかな稽古場でした。
爽やかな気候で稽古日和な朝でした。女性会員さんの参加が多く、賑やかな稽古場でした。
初心者講習を終えたFさんが一般稽古へ初参加だった為、傅位の女性会員さんに着付けと刀礼を面倒みていただき、大変助かりました。
焦らず、ご自身のペースで稽古へ参加して出来ることを少しづつ増やしていきましょう。
本日の稽古も前回に続いて身体の中心線である正中線を意識しながら、半身の正しい使い方と股関節の緩みを重点的に稽古しました。
新人さんが参加されていたので基本稽古をいつもより長く時間を取り、基本の一と二を稽古した後、形稽古は「真」「胸尽し」「野送り」を行いました。
3月1日(土) 秋葉原・居合:大隅幸一 師範
 今日は気温が高かったけど明日からは寒くなるようで体調に気を付けないといけないですね。
今日は気温が高かったけど明日からは寒くなるようで体調に気を付けないといけないですね。
また今日は東京マラソンで稽古場のそばの大通りも通行規制があって朝の参加では経路を工夫しておりました。
本日の稽古では、基本をしっかり意識して貰うようにしていただきました。
軸のブレがないように動くこと、敵に物打ちが届くような斬りをすること、斬り終わりでは敵付けをしていること、血ぶり納刀など自己流にならないように丁寧に行っていただきました。
ゆっくり意識して動くときは丁寧にちゃんと出来ていても自分の動きになると普段の癖が出たり基本から外れた動きになったりしてきましたので個別にも注意させていただきました。
一度癖が付いてしまうと直すのに多くの時間と努力が必要になりますので、最初から身に着けていけるようにしましょう。
上達するにも最初は基本から始まりますので頑張りましょう。
2月27日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 形14本を無手で動作確認後、刀を振って貰いました。
形14本を無手で動作確認後、刀を振って貰いました。
次に合わ居合で声出しし、形の中でシンプルに見える野送りを深く掘り下げ、体軸、刀の扱い、重心移動、敵との間合いを細かく確認し、私が正面より斬りつけに合わせ鎬で受け流す動作を木刀で繰り返し、居合の奥深さを感じて貰いました。
前回に続き形の名前(真、玉光)を漢字で書き順を教えました。
2月22日、23日セドナから南へ200kmに位置するアリゾナ州の州都フェニックス市で開催された10万人以上が集まる全米で最大級の日本文化を紹介するイベント『アリゾナ祭り』に初めて行って来ました。
居合道、抜刀道、剣術、柔道、弓道、合気道、空手の演武もありその様子は次回の日記で報告します。
■自宅からフェニックス市内の高速道路を降りるまで信号機は一つもありません。
アメリカは自動車大国で日本との違いを感じます。
2月24日(月) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
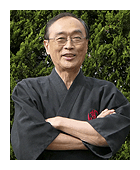 今日は祭日で稽古場は新横浜だけということもあっていつもより多くの方の稽古参加でした。それでもまだスペースには余裕があり、のびのびと安全確保で稽古できたかと思います。
今日は祭日で稽古場は新横浜だけということもあっていつもより多くの方の稽古参加でした。それでもまだスペースには余裕があり、のびのびと安全確保で稽古できたかと思います。
稽古では緩むことでの体重心の動きに合わせる剣体一致での動作を意識して稽古しています。腕の力で振ると剣と体の動きは一致しにくくなります。切り終わりでは同期できて一致しているように思いがちですが体が先に動いて後から腕の力で剣がついていく感じになってしまいがちです。そのことはよく言われる起こりが見えるということにも繋がります。緩みで動き始める体重心の移動に合わせて体全体を動かしていくことを意識して稽古してみてはどうでしょうか。
2月23日(日) 秋葉原・剣術:関戸光賀
 今日は皆さんの熱気のせいか、終わりの時間を少し超えてしまいました。
今日は皆さんの熱気のせいか、終わりの時間を少し超えてしまいました。
3月からは、御岩神社の奉納演武を意識した稽古を加えてゆきたいと思います。
春が楽しみですね。
2月23日(日) 秋葉原・居合:中野瑞岳 指導補
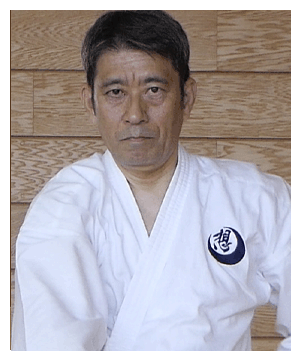 今日は連休の中日でしたが熱心な会員の方が参加下さいました。
今日は連休の中日でしたが熱心な会員の方が参加下さいました。
転身のある形は進む方向が違っていて難しいと思います。
前でしたら体も足も向いているのでイメージし易いですが横や後ろはそうは行かなくなります。特に下半身が安定してなかったりすると形の始めに体を捌いたり、頭を下げ前屈みにするだけで重心が高くなり体の軸がずれて体が振られている事を感じます。
その様に感じた時は膝、股関節を緩めて体をいつもより低めに落としみて下さい。また足捌きの足先は体の向く方向に向けて体の捩れが起こらないの様に意識して行ってみて下さい。すると軸のブレを抑えられている事を感じられ転身がしやすくなったりします。
勢いではなく体の捌きで転身出来ると良いですね。
転身は居合の中でも躍動的な動きのある形もあり醍醐味の一つです。方法は色々とあると思います試してみて自分がしっくり来る方法を見つけて下さい。
またご一緒に稽古を行って参りましょう。
2月23日(日) シニア剣法:五島博 師範
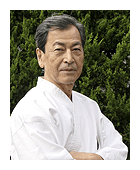 寒さの続く日曜の朝、稽古場前の公園にはシニア剣法、宗家剣法、居合稽古に参加する会員のみなさんが日向に集まり稽古場入りを待っていました。
寒さの続く日曜の朝、稽古場前の公園にはシニア剣法、宗家剣法、居合稽古に参加する会員のみなさんが日向に集まり稽古場入りを待っていました。
シニア剣法では何時もの基本稽古の後、乾坤の形の一本目と四本目、刃引きの形より華車刀を稽古しました。
仮想敵をイメージして行なう居合と異なり立ち合う相手のいる剣法では打ち込む位置、間合い、方向、タイミングなどすべてに注力し業を行なう必要があり居合とはことなる難しさがあります。
シニア剣法ではゆっくりした動きで稽古する事でより良く業が行えるよう稽古を積重ねて行きたいとおもいます。
以上シニア剣法稽古の報告です。
2月23日(日) 品川・居合:大隅幸一 師範
 あちこちで梅の花が咲いており香りも漂ってきます。
あちこちで梅の花が咲いており香りも漂ってきます。
寒い中でも春を感じさせてくれます。
本日は稽古人数が少なめでしたので走り懸りを多めに稽古してもらいました。
ゆっくりでも初めの構えの段階から力まないで動きが止まらないように意識してもらいました。
往々にして雑な動きになりがちなので、力に頼らず緩むことも大事な旨を伝え注意してもらいました。
緩みを使うことに苦労しながらも頑張って稽古しておりました。
2月21日(土) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
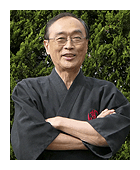 本日は基本の一、基本の二の稽古に少し多くの時間を割いて稽古しました。
本日は基本の一、基本の二の稽古に少し多くの時間を割いて稽古しました。
軸のブレを出来るだけ小さく、力で振るのではなく体重心の移動に合わせて緩みを起点にして振りぬくように注意を払っての稽古を意識してみます。基本の二では逆袈裟の切り終わりから切っ先で敵を捉えながら攻めで間合いを詰めていきます。前の足に移った体重心を感じながら緩みで次の動作に移ります。軸をしっかりコントロールしてブレが少ない動作で切り終わりはピタリと静止出来るようになりたいものです。
2月16日と20日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *16日(日)
*16日(日)
ご夫妻の初心者稽古、基本に加え形は左月、両車を新たに指導。
左月では体を開きながらの抜刀の動き、両車は股関節と膝の緩み及び刀の扱い方のポイントを稽古しました。
*20日(木)
形14本を復習し、特に向抜、夢想返しの後ろから敵を素早く切る為、頭上正中線から出ない様意識し転換する動作稽古を重ねました。
形の内、水月・左月・右、の漢字の書き順も教え、形に対しても親しみが湧くように工夫してみました。
2月15日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
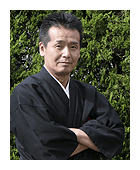 寒波が一旦収まり、今朝は柔らかな日差しと心地良い空気が漂っていました。
寒波が一旦収まり、今朝は柔らかな日差しと心地良い空気が漂っていました。
本日も20名近くが稽古に参加して、いつにも増して活気ある稽古場でした。
先月に滝野川で見学されて入会されたFさんの新人講習を関戸筆頭師範が担当し、ロシア出身で日本の古武道を学んでいるDさんの4級審査を小井指導員が審査して見事に合格されました。それぞれの目標に向けて更に精進して参りましょう。
本日の一般稽古では、身体の中心線である正中線を意識しながら、半身の正しい使い方を重点的に稽古しました。
男性会員に多くある力任せの抜刀や下半身の半身に対して上半身が正対してしまうことで身体が捻れてしまっている点を修正し、力を抜いてリラックスした状態で抜刀することを意識していただきました。
基本の一と二を稽古した後、形稽古は「真」「胸尽し」「向抜」「玉光」「陽中陰」「野送り」「前腰」を行いました。
2月15日(土) 市川・居合:平澤昂円 師範
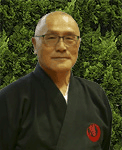 ここ数日は寒くなりました、急に稽古を始めるとケガをする恐れがあるので基本動作に時間をかけてから稽古を始めました。
ここ数日は寒くなりました、急に稽古を始めるとケガをする恐れがあるので基本動作に時間をかけてから稽古を始めました。
基本動作で足の入れ替え、半身の切り替えをしますが慣れないうちは皆さん苦労するようです、この二つの動作で重心を感じたり、正中線を理解したり、軸を意識したりしますが大切なことは体の緩みを感じ取ることだと思います。
膝の緩み、股関節の緩み会の居合を学ぶ上で欠かせない動作ですので繰り返し稽古をすることが大切と考えます。
これから御岩神社の奉納演武に向けて稽古が始まります稽古場だけでなくいろいろの経験が出来るのも居合を学ぶ楽しさの一つだと思います。
2月8日と13日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *8日(土)
*8日(土)
ご夫妻の初心者稽古、前回の稽古に加え向抜を新たに指導。
形では軸の意識と形の理合を説明しました。
ご夫妻の居合刀一式は今月末京都より届く予定が制作遅延につき来月末との連絡があり、海外での不便さを感じました。
その分届くまで基本をじっくりと指導します。
*13日(木)
今迄指導した形14本を復習し、その中で不得意な「胸尽し」の抜刀と体捌きを重点に稽古。
休憩時間を利用し「剣体一致」の動きの意識を持ってもらう為、漢字の説明も含め説明しました。
2月8日居合、9日剣術:関戸光賀
 居合では、自分の正中線を意識することが重要です。
居合では、自分の正中線を意識することが重要です。
足の位置や向きを見ると、それが意識されているかどうかが一目瞭然です。
剣術においては、敵との正中線の関係がより明確になります。
相手の正中を制することで、形が成り立ちます。
2月9日(日) 池袋・居合:中野瑞岳 指導補
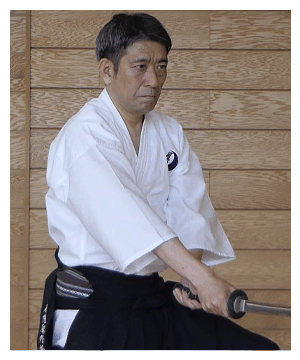 今日も冬の寒波の朝でしたが、稽古場は8階にあり入口の東側窓からの日差しはとても暖かく少し春が近づいて来た事を感じられました。
今日も冬の寒波の朝でしたが、稽古場は8階にあり入口の東側窓からの日差しはとても暖かく少し春が近づいて来た事を感じられました。
稽古で膝.股関節の緩みを意識して下さいとよく言葉を頂きます。緩みって何だろうと始めた頃よくわからなかった事を覚えています。
これが答えだと一言でおさまるものではないのでしょう、膝を曲げる、重心を下げる、軸を立てブレないため下半身を柔らかくする等々色々なものが包括された表現なのかもしれません。
また立技、座技など状態によっても様々な緩みの程度があり頃合いを見つける事も必要になります。
稽古のなかで、膝.股関節の緩みについて考えてみるのも居合の一部をより深く知る事につながっていくのではと思います。
またご一緒に稽古を行って参りましょう。
2月9日(日) 市川・居合:岩田和己 指導員
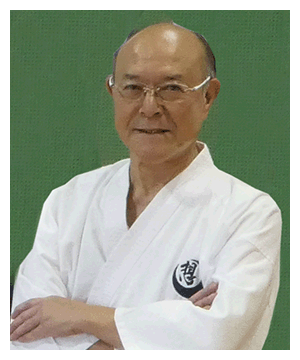 やはり2月の早朝は寒く、稽古場に行くときはつい厚着をしてしまいます。
やはり2月の早朝は寒く、稽古場に行くときはつい厚着をしてしまいます。
稽古が終わるころには気温も上がり、稽古時の火照りもあって、もう少し薄手のジャケットのほうがよかったのではと後悔します。
本日の市川参加メンバー、いつもの顔ぶれです。
基本稽古はいつものように、軸のブレ、刃筋、斬り終わりの切っ先の位置を意識しながらの素振り、抜刀については手の内を緩め、滑らかに鞘から抜けるよう繰り返しました。
形稽古についても各形の要点を伝え、ゆっくり等速で動いていただきました。
稽古形は、左月、両車、陽中陰、神妙剣の4形。
各形それぞれ難しい動きがありますが、ゆっくり何回も稽古を繰り返すことによって正しい動きが身についていくと思います。
寒さはまだ続くと思いますが、体調を崩さないよう体調管理なさって稽古を続けてまいりましょう。
2月8日(土) 秋葉原・居合:三浦無斎 師範代
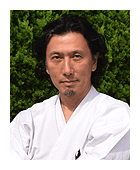 宗家稽古と同時に行われた一般稽古についてです。
宗家稽古と同時に行われた一般稽古についてです。
稽古中にもお伝えしましたが、「速さで誤魔化さない」ということをもう一度思い起こしてください。
抜刀や斬りの最終の形だけにこだわって、速く動くことで途中の体の使い方を誤魔化さないように、ってことです。
ゆっくり動いても同じ動きができるかどうか確認してみてください。最初のうちは速さを求められることはありません。
逆にスムーズに動いていけるようになれば、結果として速い動きになるはずです。
稽古回数の多い方を見て、その速さを真似したい気持ちは
十分わかりますが、求めている体の動きになってなかったり、
怪我の原因になったりします。
合宿と奉納演武が迫ってきました。
目標があるとまた気持ちが入ってくると思います。
焦らず着実に、共に精進して参りましょう。
2月1日(土) 田町・剣術:関戸光賀
 今日も伝えたいことが多く、気づけばあっという間に時間が過ぎてしまいました。
今日も伝えたいことが多く、気づけばあっという間に時間が過ぎてしまいました。
2月も変わらず、次のように稽古を続けましょう。
・けがをさせず、けがをせず。
・痛いことをさせず、痛いことをせず。
2月2日と6日 セドナ(USA)・居合:松浦章雄 指導員
 *2日(日)
*2日(日)
ご夫妻の初心者稽古、基本稽古+基本の一・二は刀と木刀で、形は真、胸尽し、円要を無手で刀を持ったと同じ様に股関節及び膝の緩みを意識し、ご自分達の刀が配達される迄手順を出来るだけ多く覚えてもらう様に稽古しました。
*6日(木)
いつもの様にストレッチ、基本稽古後、形は五用、五応、水月、前腰、夢想返し、今回初めて陰中陽を指導しましたが、これまでに五用、五応を繰り返し稽古した為、新たな形も覚えが早く感じました。
立春も過ぎセドナは春を感じる日々となりましたが、日本列島は今季最強の寒波到来と聞いております。
外出時の移動には、くれぐれもお気をつけ下さい。
2月1日(土) 田町・居合:大隅幸一 師範
 本日は2月に入り陽気もよく穏やかで梅の花も見ることができました。
本日は2月に入り陽気もよく穏やかで梅の花も見ることができました。
明日は雪が降る予報もあって天気が一変するようですので、体調に気を付けたいですね。
本日は剣法と居合の同時稽古でした。
私が担当しました居合稽古についてです。
本日の居合稽古は有傳者から新人までの幅広い層の方々でしたので、最初に共通の注意ポイントを絞って説明してから動いていただきました。
また各人の技量に応じ稽古していただき、適宜に全体を通しての注意点などについても指導をさせていただきました。
各自での動きになると斬りや所作が疎かになってきやすいので気を付けましょう。
稽古では常に自分がどうなのか注意してみましょう。
自分でも気が付けるようになれば上達も早くなるのではないでしょうか。
お互いに頑張って稽古に励んでまいりましょう。
2月1日(土) 池袋・居合:関口翠覚 指導員
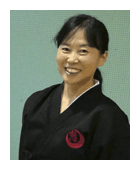 正面が鏡張りのお稽古場ですので、今日は正面だけでなく鏡を左側にしてご自分の動きを横からも確認していただきました。
正面が鏡張りのお稽古場ですので、今日は正面だけでなく鏡を左側にしてご自分の動きを横からも確認していただきました。
抜刀時の前傾斜や上下の揺れ、振りかぶりの位置など、ご自身で自覚することで指導ポイントをより理解していただけるのではないでしょうか。
開始姿勢と終了姿勢だけでなく、変化していく動きの途中も軸を活かせるような身体の使い方を身に付けたいですよね。
手の内を緩め方を繰り返し説明しましたが、力みは動きを固めてしまいますので、力に頼らない動きを意識的に行ってみてください。
明日は雪の予報が出ています。来週はずいぶん気温も下がるようですね。冬本番です。休める時はしっかり休んで次回のお稽古へ備えましょう。
1月26日と30日 セドナ・居合:松浦章雄 指導員
 *26日(日)
*26日(日)
先週に続きご夫妻の初心者稽古、居合刀は昨年11月に注文しましたが、まだ2月末頃まで待つ為、刀礼及び基本稽古は私の刀及び木刀で、初めての形「真」を無刀で股関節の使い方も含め指導しました。
*30日(木)
基本、形稽古は五用・五応と水月、前腰、及び本日初めて夢想返しを指導いたしました。
稽古終了後、各形の漢字の意味を説明し日本語の奥深さに非常に興味を示してくれました。
1月26日(日) 秋葉原・剣術:関戸光賀
 剣法は理論であり、それを形として体系化させています。
剣法は理論であり、それを形として体系化させています。
しかし、その形も毎回同じというわけではありません。
上級者は相手に応じて、速度や力加減、そして間合いを変化させていきます。
正しい稽古を成立させるためには、相手に合わせて打ち方を変えることが必要です。
そうした変化こそが、剣法の面白さだと考えてください。
1月26日(日) 秋葉原・S剣:五島博 師範
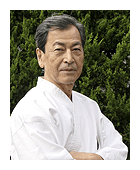 寒風がこたえる朝の天候の中、何時ものメンバーの参加がありました、前回同様、基本となる素振り、打ち受けを稽古の後、刃引きの形5本を稽古しました、立ち合う相手の何処に打ち込むのか又相手との間合いは的確か正中線の取り合いは出来ているか受けの形は正しく自身を守っているか、確認する事は沢山ありますひとつづ確認しつつていねいに稽古を継続していきましょう。
寒風がこたえる朝の天候の中、何時ものメンバーの参加がありました、前回同様、基本となる素振り、打ち受けを稽古の後、刃引きの形5本を稽古しました、立ち合う相手の何処に打ち込むのか又相手との間合いは的確か正中線の取り合いは出来ているか受けの形は正しく自身を守っているか、確認する事は沢山ありますひとつづ確認しつつていねいに稽古を継続していきましょう。
以上シニア剣法稽古の報告です。
1月26日(日) 秋葉原・居合:岩田和己 指導員
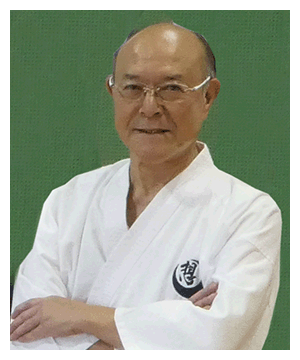 年が明けたと思ったら、すでに1月もあとわずか。
年が明けたと思ったら、すでに1月もあとわずか。
私事ですが、毎年1月は比較的のんびりできていたのですが、今年はなぜか公私ともに忙しくあっという間に過ぎてしまいそうです。
本日の昌平稽古場は、宗家剣法、シニア剣法、居合と分散して行われました。
私が担当した居合の参加者は、級から傳位と幅広い構成となりました。
基本稽古では、刀を真ん中で取る、しっかり鞘を引いての抜刀、特に逆袈裟での刃筋、斬り終わりの切先の位置など基本的な動きを確認しながら動いていただきました。
形稽古は、右、野送り、響返し、右の敵の4形。
それぞれの形のポイントとなる、転身時の軸ブレ、身を守れる抜刀、股関節の緩みによる転身等を繰り返し行いました。
以前にも書いたことがありますが、それぞれの形は基本稽古の要素が集まってできています。
基本稽古では正しく動けているのに、形稽古になるとそれが生かされていない場合が見受けられます。ゆっくりした動きの中で、一つ一つ確認しながら直すべきところを直していきましょう。
まだしばらくは寒さが続くと思われます。
皆さん、風邪などひかないよう体調管理なさってください。
1月25日(土) 滝野川・居合:宮澤和敬 師範代
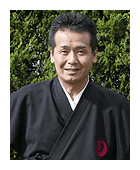 昨夜から降り続いた雨の影響もあり、肌寒く感じる朝でしたが、本日も多くの会員さんが稽古に参加されました。
昨夜から降り続いた雨の影響もあり、肌寒く感じる朝でしたが、本日も多くの会員さんが稽古に参加されました。
級から傅位まで幅広い参加があった一般稽古では、首から背骨まで軸をしっかり立て、身体の中心線である正中線を意識しながら力を入れるポイントと力を抜くポイントを明確にして動きにメリハリをつけていただきました。
抜刀時に力むことで身体のバランスや鞘引きのタイミングが崩れてバタバタしてしまう為、身体の力を抜いていただき、リラックスした状態で抜刀することを意識していただきました。
何事も自然体が大切で「無」の境地となって身体が自然に動けるようになることが理想的ですが、雑念に邪魔されて簡単のようでなかなか難しいです。心身共に精進していきましょう。
1月25日(土) 市川・居合:平澤昂円 師範
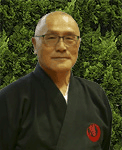 朝晩は寒いですが陽が昇ると1月とは思えない暖かな陽気です
朝晩は寒いですが陽が昇ると1月とは思えない暖かな陽気です
今日は緩みを意識して稽古をしていただきました。真向の構えから力強く振るのではなく膝のゆるみ、手の内の緩み、股関節の緩みをに注意して稽古をすると軸がぶれずに動作が行えるようになります。何か一つ注意点を決めて稽古に臨む意識が大切と考えます
最近S剣に参加したIさんと稽古の行きかえりに剣法のことをよく話します。剣法を学んで手の内の緩みがいかに大切か身に染みて感じるようになり、難しいけれど剣法の稽古が楽しみになったそうです。私も頑張らなくては。
1月23日(木) セドナ・居合:松浦章雄 指導員
 最近セドナは毎日氷点下の気温で、道場は暖房しておりますが、怪我をせぬ様、しっかり準備運動、ストレッチをしてから稽古を始めました。
最近セドナは毎日氷点下の気温で、道場は暖房しておりますが、怪我をせぬ様、しっかり準備運動、ストレッチをしてから稽古を始めました。
基本稽古及び剣術稽古の基本である体捌きを繰り返し、走り懸りの足運びをした後、形は五用、五応全てと水月、前腰を通しで行い、最後に胸尽しの抜き付けを、一拍子で抜刀する様に指導しました。
1月18日(土) 田町・居合:髙橋武風 指導補
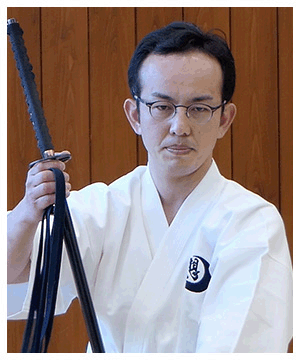 本日は20名以上と稽古に多くの方が参加頂きました。
本日は20名以上と稽古に多くの方が参加頂きました。
場所があまり広く無かった為、真、胸尽くし、左月、右を稽古いたしました。
座技の動き始めはどの形も同じく膝に重心をのせないで真上に立ち上がる様に意識しましょう。そうすると左右の転身も上手く動ける様になると思います。
まだまだ寒い日が続きますが2025年も元気に稽古して参りましょう。
1月16日.19日 セドナ・居合:松浦章雄 指導員
 ■16日(木)
■16日(木)
基本稽古、形稽古をゆっくりと丁寧に動いてもらった後、合わせ居合を初めて指導しました。
互いの息遣いと動きを感じながら、同時に動き出し、気合の発声を合わせ、同時に終わる。
いつもと違う新鮮さと緊張感を味わってもらいました。
■19日(日)
昨年12月に稽古を始められたご夫妻の稽古日です。
引き続き初心者稽古と基本の一を中心に半身を切る動き、股関節や膝の緩みを掘り下げながら指導を予定してます。
ロスアンゼルス市近郊では山火事発生で1万棟以上が被害を受け、100万世帯・事業所が停電となり過去にない大規模災害が発生中です。冬は火の元にご注意を。
1月18日(土) 赤羽・居合:関口翠覚 指導員
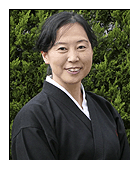 本格的な寒さが続きますね。
本格的な寒さが続きますね。
インフルエンザなど体調を崩す方が増えているようですので、体調管理は引き続き気を付けて参りましょう。
お稽古場は比較的ゆったりとスペースを使えましたので、各々のペースで振る時間を多く取りました。自分のタイミングで動ける時こそ指導ポイントを落とし込むチャンスだと思います。本日参加の皆さまはとても丁寧に動いており、お伝えしたポイントを確認している様子が伝わってきました。今後もただ繰り返し動くだけの時間にならないように心がけてください。
軸を崩さず、正しい刀捌きや足捌きを体に染み込ませてゆけば、自然に動きが素早くなっていくはずです。急がば回れですね。
年が明けて新春稽古会、この先も合宿と奉納演武、演武会とイベントが続きますね。今年も楽しみです。
1月13日(月) 新横浜・居合:和田冠玄 指導員
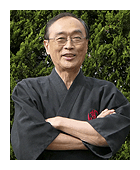 本日は稽古場近くの横浜アリーナで成人式の催し物があり、稽古場に向かう途中、振り袖や羽織袴の姿を多く見かけました。艶やかな着物姿で少しぎこちない歩き方に微笑ましさも感じます。
本日は稽古場近くの横浜アリーナで成人式の催し物があり、稽古場に向かう途中、振り袖や羽織袴の姿を多く見かけました。艶やかな着物姿で少しぎこちない歩き方に微笑ましさも感じます。
さて稽古はいつものように「軸の維持、そして柄頭、前に出る足先、膝で敵を捉えて」を意識して稽古してもらっています。曖昧な意識で稽古を続けると悪い癖が出てしまいがちです。自身の良くない癖を意識して繰り返し稽古することで、出来るだけ正しく動けるよう精度を上げられればと思います。
本日は、新横浜場所の稽古始め、本年もよろしくお願いします。
1月12日(日) 赤羽・居合:三浦無斎 師範代
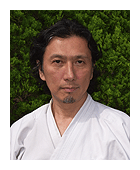 本日は、稽古回数の少ない方から有傳者まで幅広い方々が参加されました。
本日は、稽古回数の少ない方から有傳者まで幅広い方々が参加されました。
それゆえ、いつもよりお伝えしたポイントが多めだったかと思います。
当然のことながらそれら全部を当日の稽古内で確認できませんし、ましてや次の稽古に繋げるのはもっと困難です。
でも、その日にピンと来た1つか2つーなんでも良いのですが、ーをその日の稽古で確認すると共に、できれば次回まで覚えておいて頂ければと思います。
そうした項目が増えていくと自分自身のチェックリストが出来上がってきます。それを日々更新していくんですね、稽古って。
私のリストも長くなるばかりです。
今年も引き続き一緒に精進して参りましょう。
1月12日(日) 市川・居合:平澤昂円 師範
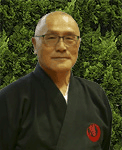 2025年成人式に向かう晴れ着姿をながめながら初めての市川稽古です。今年も明るく元気に稽古をしていきましょう。
2025年成人式に向かう晴れ着姿をながめながら初めての市川稽古です。今年も明るく元気に稽古をしていきましょう。
稽古は18本の形を繰り返し稽古をしていきます、同じ形でも稽古をしていくと少しずつ違いが感じられます、動きを真似することから始めますがそこで出来たと思うと進歩は止まります、なぜならそれは似たものでしかないのです。
個人差はありますが稽古を重ねていくと初期とは違う形が求めるものを感じられてくると思います。そんな積み重ねが居合の世界に導いてくれると信じています。
今年もよろしくお願いします。
1月12日(日) 品川・居合:田澤尊伯 指導補
 寒さが厳しくなる時候、空が高く感じられ、冬らしく気持ちが良いですが、風が身に沁みますね。
寒さが厳しくなる時候、空が高く感じられ、冬らしく気持ちが良いですが、風が身に沁みますね。
本日の稽古は、基本稽古および、形稽古も形毎で、少し時間を取りながら進めました。
形稽古は、真、胸尽し、向抜、野送り、前腰(稽古順)。
全体を通じて、中心線を意識して、動きを確認するようにして頂きました。仮想敵を捉える意味でも大切。
引き続き、ご一緒に稽古をしていきましょう。
1月11日(土) 田町・剣法:関戸光賀
 今日は小太刀の延長線上にある無手の稽古も行いました。
今日は小太刀の延長線上にある無手の稽古も行いました。
体軸を中心として、体が澱みなく動いていればOKです。
居想会で一番重い得物は薙刀です。薙刀も小太刀そして無手でも基本的な体の使い方は一緒です。
1月11日(土) 田町・居合:大隅幸一 師範
 本日の朝は寒さが厳しかったですが稽古帰りには日差しがあり暖かさを感じられました。
本日の朝は寒さが厳しかったですが稽古帰りには日差しがあり暖かさを感じられました。
本日は宗家剣法、シニア剣法と一般居合の三つの稽古が同時に行われました。
私が担当しました一般居合稽古についてです。
本日の一般居合は、初傳位のほかに新人の参加もありましたので、各自のレベルに応じて指導しました。
全体を通しては基本の動きと所作はしっかりと注意して稽古するようにしていただきました。
基本と形稽古では、本日特に注意していただく点を説明してから、最初の一本をゆっくりした動きで確認してもらいました。
その後は各自のペースで動いていただきました。
各自のペースになると力が入って軸がブレたりしますので、稽古中は常に基本が疎かにならないように注意しましょう。
基本は全てに通じますのでしっかり身に付くよう稽古してまいりましょう。
1月11日(土) 池袋・居合:中野瑞岳 指導補
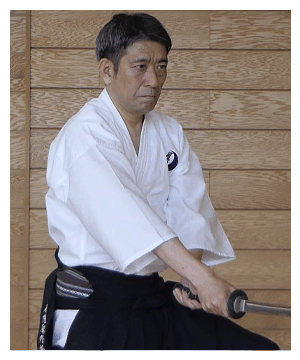 本日は池袋の初稽古でした、稽古回数を重ねた方々で希望もあり18本通しを行いました。正面全体に鏡が有りましたので体の向きを正面、横向きに都度変えて体の軸のぶれ構えや上下動を確認しながら稽古を進めて頂きました。
本日は池袋の初稽古でした、稽古回数を重ねた方々で希望もあり18本通しを行いました。正面全体に鏡が有りましたので体の向きを正面、横向きに都度変えて体の軸のぶれ構えや上下動を確認しながら稽古を進めて頂きました。
鏡は自身の写った姿に観入ってしまうと本来の注視すべき所が見えなくなり目的から外れてしまう事がありますので活用には注意が必要です。
自身の全体像が見えて状態を確認するにはとても良いものですので補正した体の姿勢や股関節、手足の状態を確認して体に落とし込んで鏡が無くても出来る様に意識していくと良いと思います。
いずれは鏡が無くてもしっかり体に染み込んでいて姿、形が自身の頭の中に投影されていくのではないでしょうか。
本年もご一緒に稽古を行って参りましょう。
1月2日(木) セドナ・居合:松浦章雄 指導員
 明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
アメリカは1月1日のみニューイヤー祭日ですが、1月2日から平常に戻ります。
本日は新年初稽古で、腹抜きの稽古を中心としました。
胸尽しでは、股関節を意識し右半身の捌き抜刀、重心が真ん中になる様繰り返しました。
稽古全体では頭が上下しない様に気をつけてもらいました。
年末のクリスマスから新年にかけ毎日晴天で暖かく昨日は新年のハイキングを楽しみました。
本年もどうぞ宜しくお願い申しあげます。